
カルシウムの推奨量や多く含む食品は?とり入れる際に気をつけたいポイント
カルシウムは人の体に最も多く存在するミネラルで、生きるために欠かせない栄養素です。 この記事では、カルシウムの推奨量やカルシウムを多く含む食品などについて解説しています。
カルシウムは、人の体の中に最も多く存在するミネラルで、乳製品や大豆製品から多く摂取できます。健康のためにはカルシウムだけではなく、さまざまな食品を組み合わせてバランスよく栄養素を摂取することが大切です。
この記事では、カルシウムの特徴や推奨量、カルシウムを多く含む食品、効率よく摂取するポイントなどを詳しく解説します。
さらに、カルシウムを手軽にとり入れられる家庭料理のレシピもご紹介します。主菜や副菜、ヘルシーなおやつまで、毎日の食事にとり入れやすいメニューを揃えました。
1. カルシウムとは

カルシウムは人体の中に最も多く存在するミネラルです。
体重の1~2%を占めており、50kgの成人で約1kgものカルシウムが体内に存在するのです。そのうちの99%は骨や歯にヒドロキシアパタイト(カルシウムとリン酸を主成分とする無機物質)として存在し、骨や歯の形成に必要な栄養素です。
最も多く存在するということは、それだけ体の中で使われる機会も多いということです。
カルシウムが不足すると、健康に影響をおよぼすため、適量つまり推奨量を摂取することが大切です。カルシウムを多く含む食品や、より良い摂取方法は後述するので、ぜひ参考にしてください。
2. カルシウムの1日の摂取目安量
カルシウムは年齢や性別によって必要量が異なり、厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版) 」では、以下のように策定しています。
【1日の推奨量(mg)】
|
年齢 |
男性 |
女性 |
|
8~9歳 |
650 |
750 |
|
10~11歳 |
700 |
750 |
|
12~14歳 |
1,000 |
800 |
|
15~17歳 |
800 |
650 |
|
18~29歳 |
800 |
650 |
|
30~49歳 |
750 |
650 |
|
50〜64歳 |
750 |
650 |
|
65〜74歳 |
750 |
650 |
|
75歳以上 |
750 |
650 |
*出典:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」 カルシウムは、関心をもって摂取しなくていけない栄養素のひとつです。乳製品や小魚などが大切な給源となっています。 カルシウムといえば、牛乳やチーズをイメージする方が多いのではないでしょうか。牛乳を原料とする乳製品は、カルシウムが豊富に含まれており、体への吸収率も高い食品です。 食品 100g当たりの含有量(mg) チェダーチーズ 740 プロセスチーズ 630 モッツァレラチーズ 330 生乳 140 ヨーグルト 140
*出典:文部科学省「食品成分データベース」 乳製品は調理をせずに摂取できるものも多いため、手軽にとり入れやすい食品です。 カルシウムは一部の緑色の葉野菜からも摂取できます。 かぶの漬けもの 240 茹でた大根葉 220 茹でた小松菜 150 ほうれん草の油炒め 130 チンゲン菜 100
*出典:文部科学省「食品成分データベース」 大根葉や小松菜、ほうれん草は生の方がカルシウムは豊富ですが、生では食べにくさもあるため、調理して摂取すると良いでしょう。 乳製品に比べると吸収率が低くなりますが、海藻類にもカルシウムが含まれます。 食品 100g当たりの含有量(mg) 焼き海苔 280 昆布の佃煮 150 寒天 120 干しひじき 90 わかめ 70
*出典:文部科学省「食品成分データベース」 海藻はそのまま食べるのは難しいものが多いため、佃煮や和え物にして食べるのがおすすめです。 乾燥して丸ごと骨まで食べられる小魚はカルシウムを多く含みます。煮干しやしらす干しは食べやすい食品のため、普段の食事量が減っている場合には積極的に摂取してください。 食品 100g当たりの含有量(mg) かたくちいわしの煮干し (ちりめんじゃこ) 2,200 さくらえびの煮干し 2,000 しらす干し 520 焼きししゃも 380
*出典:文部科学省「食品成分データベース」 小魚は、カルシウムだけでなくDHAやEPAも豊富に含んでいます。 大豆製品と言えば、たんぱく質を多く含むイメージが強いかもしれませんが、実はカルシウムも多く含んでいます。カルシウムの吸収率は乳製品の次に高いことも特長です。 食品 100g当たりの含有量(mg) 油揚げ(焼き) 320 おから 310 がんもどき 270 きな粉 190 木綿豆腐 93 糸引き納豆 90 絹ごし豆腐 75
*出典:文部科学省「食品成分データベース」 油揚げは味噌汁の具材や煮もの、焼き物などさまざまな料理に活用でき、おからはハンバーグやコロッケの具材として使えます。 カルシウムを効率良く摂取するためには、以下のポイントを押さえると良いでしょう。 摂取したカルシウムを効率良く吸収するために、ビタミンDは必須の栄養素です。ビタミンD不足の状態では、カルシウムの吸収率が低下してしまいます。ビタミンDはきのこ類や魚類に多く含まれているため、カルシウムを含む食品と合わせて摂取しましょう。 カルシウムの体内への吸収は主に小腸で行われますが、成人の場合その吸収率は20~30%程度にとどまることがわかっています。 カルシウムを多く含む食品を意識して摂取しても、吸収を妨げる食品を一緒に過剰に摂取していると、効率良く体に吸収できない可能性があります。 カルシウムを効率よく摂取できる、おすすめの家庭料理をご紹介します。主菜となるメイン料理からおやつまで、バラエティ豊かなレシピを揃えました。 鮭ときのこのクリームシチュー カルシウムとビタミンDを同時に摂取でき、彩り豊かな野菜も一緒に楽しめる栄養豊富な一品です。 【材料2人分】(カルシウム含量:約400 mg) 【作り方】 チンゲン菜とちりめんの中華炒め カルシウムたっぷりのちりめんじゃこと相性抜群のチンゲン菜を組み合わせた、手軽に作れる副菜メニューです。ちりめんじゃこの塩味と野菜の甘味が絶妙なバランスで、ご飯のおかずにぴったりです。 【材料4人分】(カルシウム含量:約760 mg) 【作り方】 豆腐のドーナツ カルシウム豊富なスキムミルクと豆腐を使用した、罪悪感なく楽しめるヘルシーなドーナツです。砂糖不使用でも、豆腐の自然な甘味が活かされたやさしい味わいに仕上がります。 【材料6個分】(カルシウム含量:約540 mg) 【作り方】 【アレンジポイント】 カルシウムの推奨量や多く含む食品、効率よく摂取するポイントはご理解いただけましたでしょうか。
カルシウムは、成長期の10代の推奨量が特に高くなる栄養素です。30~70代の男性は1日に750mg、15歳以上の女性は650mgが推奨量であることがわかります。一方で、具体的な量がピンとこない方もいるかもしれません。
以下にカルシウムを多く含む食品と含有量を紹介するので、推奨量とあわせて覚えておくと良いでしょう。 3. カルシウムを多く含む食品は?

さらに、ひとつの食品に限定せずに複数の食品をバランス良く食べると、カルシウム以外の栄養素の摂取にもつながります。紹介する内容を参考に、さまざまな食品をとり入れましょう。
この項目では、カルシウムを多く含む食品を以下の分類ごとに解説します。
カルシウムを多く含む食品①:乳製品
主な乳製品のカルシウム含量は以下のとおりです。
しかし、牛乳はにおいが苦手で飲めない人もいるかもしれません。もし牛乳のにおいが苦手な場合は、冷やすか温めて飲む方法がおすすめです。人肌程度の温度では、においをより感じやすくなるため、温めるときは熱めにしましょう。カルシウムを多く含む食品②:葉野菜
葉野菜のうち、カルシウムを多く含む食品は以下のとおりです。
食品
100g当たりの含有量(mg)
カルシウムを多く含む食品③:海藻
海藻類にはカルシウムだけでなく、食物繊維やミネラル、ビタミンも豊富に含まれるため、健康のために摂取してほしい食品です。
カルシウムを多く含む食品は以下のとおりです。
焼き海苔は手軽に食べられ、おにぎりやお弁当にとり入れやすい食材として人気があります。ひじきは煮ものや炒め物、わかめは味噌汁の具材として日常的に使用しやすい食品の代表といえるでしょう。カルシウムを多く含む食品④:小魚
小魚のうち、カルシウムを多く含む食品は以下のとおりです。
(半乾燥品)
煮干しは出汁としても活用でき、残った出汁殻も佃煮にすれば丸ごと食べられるのが特徴です。しらす干しは丼や炒め物、サラダのトッピングとしても使いやすく、焼きししゃもは食卓のおかずとして親しまれています。カルシウムを多く含む食品⑤:大豆製品
大豆製品のうち、カルシウムを多く含む食品は以下のとおりです。
きな粉は牛乳や豆乳に入れたり、餅やわらび餅にかけたりと、デザートとしても楽しめるでしょう。豆腐は和洋中さまざまな料理に使える万能食材で、毎日の食事にとり入れやすいのが特徴です。 4. カルシウムを摂取する際のポイント
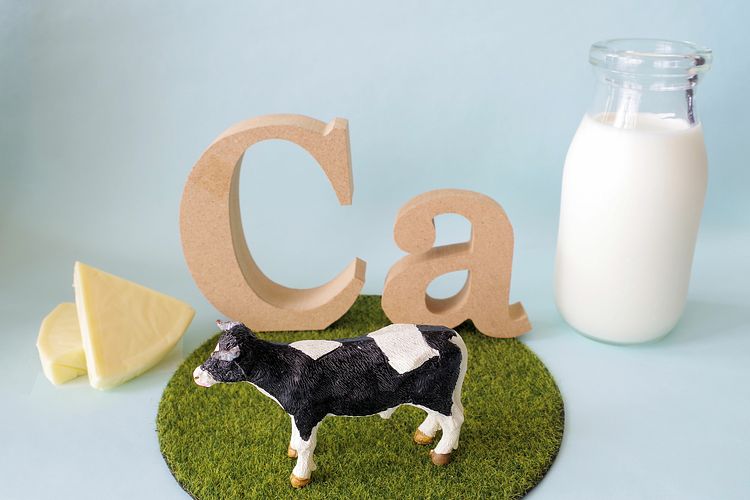
ビタミンDを一緒に摂取する
また、カルシウムを効率良く摂取するためには、カルシウムの吸収率も大切です。カルシウムを多く含む食品の項目でも解説したように、吸収率の高い食品は乳製品や大豆製品です。一度に摂取しようとせず毎食バランスよくとり入れる
また、体内では活性型ビタミンDや各種ホルモンの働きにより、血液中のカルシウム濃度が一定に保たれるしくみが備わっています。そのため、一度に大量のカルシウムを摂取しても効率的な吸収は望めません。毎食バランスよくとり入れることで、着実な吸収が期待できるのです。カルシウムの吸収を妨げる食品の摂り過ぎに気をつける
カルシウムの吸収を妨げるのは、リンを多く含む食品です。リンはインスタント食品やスナック菓子などに多く含まれているため、摂りすぎには注意しましょう。
また、カルシウムをほとんど含まない食品も知っておくと日々の食生活の参考になります。肉類や米・麦などの穀類、果物にはカルシウムがほとんど含まれていません。
しかし、たんぱく質やビタミンなど、そのほかの栄養素は摂れるため、バランス良くさまざまな食品を摂取しましょう。5.カルシウムを多くとり入れられるレシピ
どれも手軽に作れて栄養たっぷり。毎日の食事にとり入れやすいレシピのため、ぜひおためしください。
6.バランスよくカルシウムを摂取しよう

カルシウムは体内に最も多く存在するミネラルです。小魚、海藻や葉菜にも多く含まれていますが、体への吸収率が高いのは乳製品や大豆製品です。
しかし、小魚、海藻や葉菜をとり入れることで、バラエティが高くかつ栄養バランスが良い食事を続けることができます。
まずは日々の食生活の中で、カルシウムを意識的に摂取しましょう。





