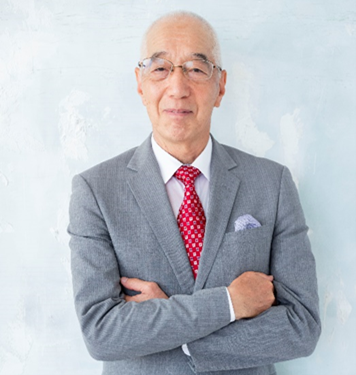EPA(エイコサペンタエン酸)とは?1日の摂取目安量や含まれる食品、食べ方のポイントも解説
EPAは、エイコサペンタエン酸と呼ばれる必須脂肪酸です。体内では作られないため、日々の食事から摂らなければなりません。 EPAはn-3系脂肪酸のひとつで、青魚類に多く含まれる成分です。 この記事では、EPAの基礎知識や1日の摂取目安量、多く含まれる食品、摂取時のポイントを解説します。
EPAはエイコサペンタエン酸と呼ばれる必須脂肪酸で、健康の維持のために必要な成分です。
しかし、体の中ではほとんど作られないため、食事から摂取しなければいけません。
EPAは魚の油に多く含まれており、いわしやさば、さんまなどの青魚類から摂取できます。
この記事では、EPAの基礎知識や1日の摂取目安量、多く含まれる食品、摂取する際のポイントを解説します。
EPAについて詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
1.EPAとは?

EPAとは「エイコサペンタエン酸」と呼ばれる成分 で、体内でほとんど作られない「必須脂肪酸」のひとつです。
またEPAは、いわしやさば、さんまなどの青魚類の油に多く含まれます。
必須脂肪酸はEPAのほかにDHAなどがあり、詳しい分類は以下の表のとおりです。
| 脂肪酸 |
必須脂肪酸 (不飽和脂肪酸) |
一価不飽和脂肪酸 体内で飽和脂肪酸から合成可能) |
オレイン酸 (おもに植物油に含まれる) |
| 多価不飽和脂肪酸 (体内でほとんど合成できない) |
n-3系:EPA、DHA、α-リノレン酸 (おもに海水魚や植物油に含まれる) |
||
|
n-6系:リノール酸、γ-リノレン酸、 アラキドン酸 |
|||
| 飽和脂肪酸 | おもに動物の油に含まれる | ||
2. EPAを含むn-3 系脂肪酸の1日の摂取目安量
1日当たりの摂取目安量は、厚生労働省による「日本人の食事摂取基準(2025年版)」で策定されています。
しかし、EPA単体での摂取目安量が定められているのではなく、DHAやα-リノレン酸などのn-3系脂肪酸を合わせたものが発表されています。
EPAなどのn-3系脂肪酸の1日の摂取目安量は以下の表のとおりです。
| 年齢 | 男性(g) | 女性(g) |
| 18~29歳 | 1.98 | 1.48 |
| 30~49歳 | 2.07 | 1.66 |
| 50~64歳 | 2.28 | 1.89 |
| 64~74歳 | 2.62 | 2.25 |
| 75歳以上 | 2.28 | 1.95 |
出典:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」 上記の数値だけでは、具体的な摂取量のイメージがわきにくい方もいるかもしれません。 EPAを多く含む食品と含有量は以下の表のとおりです。 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2015年版(七訂)脂肪酸第2章第1表魚介類」 日々の食生活で取り入れやすい食品を紹介しましたが、EPAを摂取する際はいくつかポイントがあります。 EPAは体内では作られない必須脂肪酸のひとつで、食事から摂らなければ補給できません。 EPAを効率良く摂るには、調理方法を工夫することも大切です。 ※出典:日本脂質栄養学会「魚の加熱調理では、DHAやEPAがどれくらい減るか?」 「EPA(エイコサペンタエン酸)」は必須脂肪酸のひとつで、体内でほとんど作られないため、食品から摂取しなければならない成分であるとお伝えしてきました。 ファンケルの「DHA&EPA」と「EPA&DPA」をご紹介します。 気になる生活習慣のためには、スムーズな流れを保つことが大切。サラサラの青魚成分のEPA(エイコサペンタエン酸)を高配合。1日の目標量の1/3が摂れます。さらに、EPAよりも高いサラサラ成分のDPA(ドコサペンタエン酸)に着目。気になる生活習慣に働きかけます。 見る・考える・学ぶなど、スムーズな日々に欠かせない「DHA」と「EPA」は青魚に多く含まれる成分。。食事で不足しがちな成分をしっかり補えるように、「DHA」と「EPA」を合計で500mg配合しました。さらに酸化しやすいDHAを「オリーブ葉エキス」により守ります。独自の配合で、4.2倍の吸収量を実現しました。
次の項目で、EPAが多く含まれる食品と含有量も紹介するので、摂取目安量と併せて覚えておくと良いでしょう。 3. EPAが多く含まれる食品

さばやさんま、いわしなどの青魚に多く含まれていることがわかります。
食品名
可食部100g当たりのEPA(mg)
さば類(開き干し)
2,200
さんま(皮なし、刺身)
1,500
くろまぐろ(脂身、生)
1,400
ぶり(成魚、生)
940
にしん(生)
880
まいわし(生)
780
4. EPAを摂取するポイント

以下で解説する2つのポイントを参考に、効率良くEPAを摂取してください。
日々の食事から意識的に摂取する
先述したEPAが多く含まれる食品を参考に、意識的に日々の食事でEPAを取り入れてください。
ただし、日々の食生活で意識してEPAを摂ろうと思っていても、魚が苦手な方は、毎日魚を食べるのは難しいかもしれません。
EPAを満足に摂れていないと感じるときは、サプリメントを取り入れる方法もあります。原則として食生活を大切にする姿勢を忘れず、必要に応じて上手くサプリメントを活用してください。調理方法を工夫する
EPAは、加熱すると量が減っていく特徴があります。例えば、焼魚では約20%、揚げ魚では約50%のEPA量が減少するといわれています。
そして、油を使う調理法では、魚の油に含まれるEPAが流れ出るため、EPAの量が減るといわれています※。
EPAをより多く摂取したいならば、食べられるものは生での摂取がおすすめです。生で食べられる調理法には、刺身やカルパッチョなどがあります。
生が苦手な場合は、汁物にして汁ごと摂取することでEPAを効率良く取り入れることができます。
5.食べ方を工夫して、食事からEPAを摂取しよう
EPAが多く含まれる魚類を食べる際は、調理法を意識することも大切です。ご紹介したように、EPAは加熱調理すると量が減少してしまうため、生で食べられる食品であれば刺身やカルパッチョとして食べると良いでしょう。
加熱が必要な魚は、汁物にして汁ごと取り入れたり、焼いて食べたりする調理方法がおすすめです。食べる際のポイントも意識して、上手くEPAを取り入れてください。
青魚の栄養が不足しがちな方に
ファンケルの「DHA&EPA」と「EPA&DPA」をご紹介
DHAとEPA、DPAは体内では作られないため、食事で摂る必要のある必須脂肪酸に分類されており、青魚に多く含まれています。
ファンケルの「DHA&EPA」は、DHAとEPAが合わせて500㎎配合されています。考えることの多い大人からクリアに過ごしたい中高年まで、あらゆる年代の方に大切な成分が含まれているサプリメントです。
加熱調理で減少しやすいDHAとEPAですが、ファンケルの「DHA&EPA」は独自の自己乳化製法技術で、体内での吸収にもこだわりました。
また「EPA&DPA」は、EPAを334mg配合しています。EPA・DHA・DPAの3つの成分が、めぐりのある毎日をサポートします。
「DHA&EPA」「EPA&DPA」ともに1日5粒目安で手軽に取り入れることができ、食事からの摂取が不足していると感じる日にも手軽に青魚の成分が補えます。
クリアな毎日を過ごしたいとお考えの方や、スムーズな日々のために取り入れたい方も、日々の食生活と組み合わせて「DHA&EPA」「EPA&DPA」を上手く活用してください。
EPA&DPA
30日分1,296円(税込)DHA&EPA
30日分1,944円(税込)