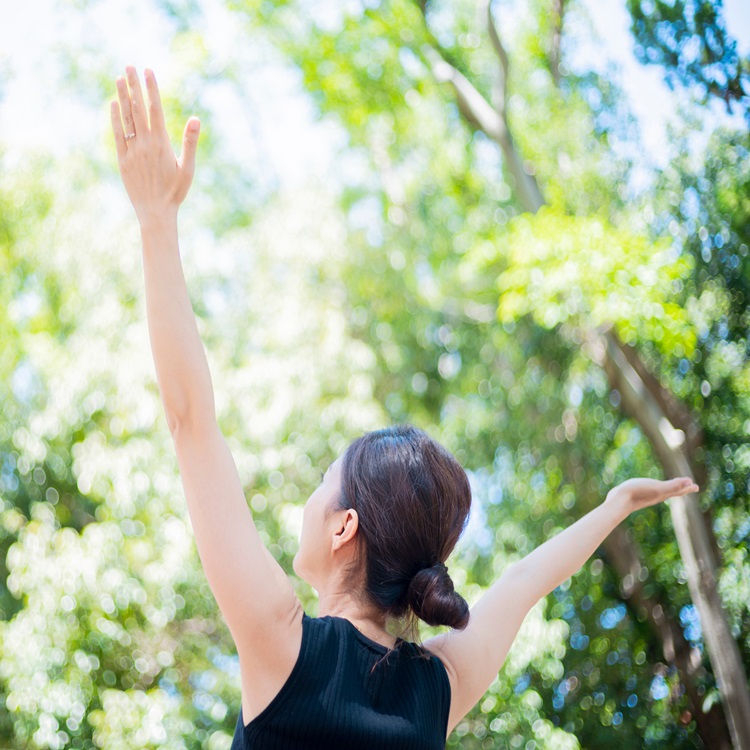ビタミンDと日光浴の関係性とは? 日差しを浴びる時間や注意点を解説
骨の健康に欠かせない栄養素であるビタミンD。日光浴によって体内で生成できることをご存じでしょうか? この記事では、ビタミンDと日光浴の関係性、日光浴の時間や注意点、日々の食事からビタミンDを摂る際のポイントをご紹介します。
1. ビタミンDとは?
ビタミンDは、骨の健康を維持するために欠かせない栄養素です。カルシウムやリンの吸収を促進し、骨の形成と成長をサポートしています。また、血液中のカルシウム濃度を一定に保つことで、筋肉の収縮や神経の伝達を正常に行なう働きも。ビタミンDの不足はカルシウムの吸収に関わります。骨の健康のためにもしっかり摂りたいところです。
また、ビタミンDは紫外線を浴びると体内で生成されるという特徴があります。しかし、日光を浴びる機会の減少やこまめな紫外線対策によって、日本人のビタミンD摂取量は不足傾向にあるため、意識して摂取・生成したい栄養素です。
2. ビタミンDと日光浴の関係性
ビタミンDは食品から摂取するだけではなく、日光浴によって体内で生成することができます。日光を浴びて紫外線が肌に当たると、体内のコレステロールを材料として肌でビタミンDが生成されます。
紫外線により生成されるビタミンDの量は調節されており、必要以上に体内で作られる心配はありません。日中に日差しを浴びるだけでいいので、手軽にビタミンDを生成できることもうれしいポイントです。
3. ビタミンDをつくるにはどれくらい日光浴が必要?

ビタミンDをつくるには夏で5〜10分程度、冬で30〜40分程度、日光を浴びる時間が必要といわれています。季節によって紫外線の量は変わるため、日差しの強い夏は木陰で10分程度、冬の日差しが弱いエリアでは最低でも1時間程度の日光浴が適当といえるでしょう。近年ではこまめなUV対策などが原因の一つとなり、日本人のビタミンD摂取量が不足しがちになっている可能性があります。季節を意識しながら、積極的に日光浴を取り入れたいところです。
また、地域によっても必要な日光浴の時間が異なります。特に北日本は日照時間が短いため、ビタミンDを生成するための日光浴には時間がかかる傾向があります。例えば冬の札幌では、正午頃でも茨城県のつくばの3倍以上の日光浴が必要ともいわれています。冬季の北日本では、積極的な日光浴が必要でしょう。
参考:ビタミンDと日光浴(一般社団法人北海道薬剤師会)
4. ビタミンDをつくるための日光浴の方法
ビタミンDをつくるための日光浴は、日焼け止めを塗らずに「顔」と「手の甲」に日差しを当てるのが簡単な方法ですが、日やけやお肌のトラブルのことを考えるとなかなか取り入れにくいものです。
そこでおすすめしたいのが、手のひら日光浴です。手のひらは体の他の部分と比べ、日やけの原因となるメラニン色素が少ない部位で日やけの心配が少ないのが特徴。夏なら5分程度、冬なら30分程度、手のひらを太陽光に当てましょう。一気に浴びなくても、細切れでもOK。窓から手を出すだけでもかまいません。ただし、手のひらには日焼け止めを塗らないようにしましょう。
参考:ビタミンD生成・紅斑紫外線量情報(国立環境研究所・地球環境研究センター)
5. 日光浴をする際の注意点

ビタミンDを生成するために必要な日光浴。ここでは適切に行なうための注意点をご紹介します。時間帯や日焼け止めの活用方法、食事から摂取する際のポイントなどを詳しく解説します。
柔らかな日差しを浴びよう
日差しが強く、紫外線量が多い時間帯に日光浴をすると、肌や目に悪影響を及ぼします。真夏の午後など太陽が高い時間帯に強い日差しを浴びるのは、特に危険です。
そのため、心身ともに健康的に日光浴を行なうには、紫外線量が比較的少ない「午前中〜正午」くらいまでの穏やかな日差しを浴びるようにしましょう。特に夏は日差しが強いため、ぜひ「早朝」の時間帯に。直射日光が当たらない木陰での日光浴も、日差しが柔らかくおすすめです。
日光の浴びすぎはNG
適切な日光浴はビタミンDを生成できるメリットがある一方で、日光を浴びすぎると紫外線による体へのデメリットもあります。
日光浴で紫外線を浴びすぎると、シワやたるみなどの肌の老化、目への影響が出る原因となることも。
地域によって異なりますが、夏は15〜30分程度、冬は80〜100分程度の日光浴で、皮膚に有害な作用が現れる可能性が指摘されています。体に悪影響を及ぼさない適切な範囲で日光浴をおこない、紫外線を浴びすぎないよう注意しましょう。
日焼け止めは上手に活用
ビタミンDを生成する紫外線と日やけをする紫外線はほぼ同じ。日焼け止めを塗っているとビタミンDがうまく作られないため、日焼け止めを塗らずに日光浴をするのが効果的といわれています。しかし、紫外線によるシミやシワなどの肌への影響も気になるものです。
そんなときは、先ほどご紹介した手のひら日光浴がおすすめです。「顔」にだけ日焼け止めを塗り、日やけの原因となるメラニン色素が少ない「手のひら」には日焼け止めを塗らず、日光が当たるようにしてみましょう。そうすることで、顔の日やけを避けながらビタミンDを効率良く生成できます。
日焼け止めを使うときは、屋外に出る前に塗るのがポイント。一円玉くらいの量を2回にわけて塗りましょう。顔の数箇所に置いて、伸ばしながら塗ると塗りムラができません。太陽光が当たりやすい鼻の頭などは念入りに塗るのがおすすめです。
普段の食事などでも意識しておぎなう

1日に必要なビタミンDの量は、日光浴で生成される量と食事から摂取する量を合わせて10〜20μg程度。日光浴で生成されるビタミンDのみでは足りないため、日々の食事からも意識して摂取しましょう。ビタミンDが多く含まれている食品は、以下のとおりです。
| 食品 | 1回の摂取量の目安 | 含有量 |
| 焼鮭 |
80g(1切れ) |
30.4μg |
| うなぎの蒲焼 |
100g(2/3尾) |
19.0μg |
| いわしの丸干し |
30g(1尾) |
15.0μg |
| 焼さんま |
100g(1尾) |
13.0μg |
| 乾燥きくらげ |
2g(2枚) |
1.7μg |
| 干ししいたけ |
6g(2個) |
1.0μg |
参照:文部科学省「食品成分データベース」
特に多く含まれている主な食品は魚類。焼鮭やうなぎの蒲焼き、焼さんまなどは、1度の食事で摂取する量で1日に必要な量のビタミンDを摂取できます。
また、魚類ほどではないものの、きのこ類もビタミンDが豊富。ビタミンDは脂溶性で熱に強いため、乾燥きくらげや干ししいたけなどは水で戻してソテーにしたりフライにしたり油で調理するとより吸収が良くなります。
ただし、それ以外でビタミンDを豊富に含む食品は限られています。そのため、ビタミンD不足を解消するならサプリメントでおぎなうこともおすすめです。
6. まとめ
丈夫な骨をつくるために大切なビタミンD。日本人に不足しがちな栄養素でもあるため、食事はもちろん、日光浴でもおぎないたいものです。日光浴では日差しを浴びる時間が少ないと必要な量のビタミンDを生成できませんが、浴びすぎても肌に悪影響を及ぼします。季節や天気を考慮しながら、適切な時間の範囲内で行ないましょう。この記事を参考に、上手に日光浴を取り入れながら日々の健康にお役立てください。