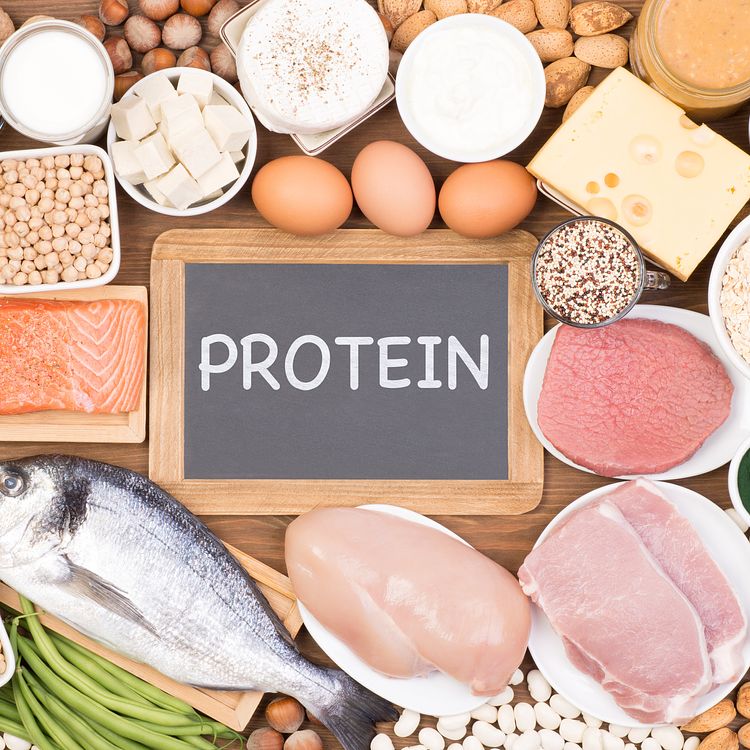
たんぱく質は1日にどれくらい必要?男女別・年齢別の適切な量や簡単献立例も
1日に必要なたんぱく質の摂取量は男女で大きく異なります。この記事では、性別・年齢別の適切な摂取量と、具体的な食品例や簡単レシピをご紹介します。 忙しい毎日でも効率良くたんぱく質を摂取するコツをチェックしましょう。
たんぱく質は筋肉や皮膚、髪などの体の組織を構成する重要な栄養素です。私たちの健康を維持するために欠かせないものですが、毎日の食事からどれくらいの量を摂取すべきか、正確に把握している方は意外と少ないのではないでしょうか。
実は、必要なたんぱく質量は性別や年齢、さらには日々の生活習慣によっても異なります。この記事では、男女別・年齢別に必要なたんぱく質の摂取量や、その量が具体的にどのような食品にどれくらい相当するのかをわかりやすく解説します。
さらに、日常の食事で効率良くたんぱく質を摂取するためのレシピやコツもご紹介しますので、日々の食生活の参考にしてください。
1. たんぱく質は1日にどのくらいとり入れるべき?
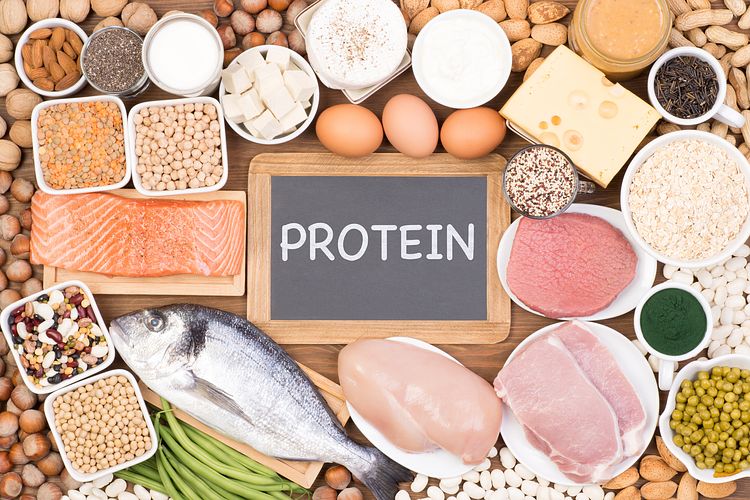
私たちの体を構成する重要な栄養素のひとつであるたんぱく質は、毎日適切な量を摂取することが大切です。厚生労働省の指針によると、1日の総エネルギー摂取量の13〜20%をたんぱく質から摂るのが理想的とされています。
たんぱく質の推奨量は性別や年齢によって異なります。体格や日常の活動量、運動習慣によっても必要量は変わってきます。
ここでご紹介する数値はあくまで目安として参考にしてください。
成人男性の推奨量は65g
厚生労働省が策定した「日本人の食事摂取基準(2025年版)」によると、成人男性(18~64歳)のたんぱく質の推奨量は1日当たり65gと策定されています。この数値は平均的な日本人男性の体格や活動量などを考慮して策定されたものです。
一方、65歳以上の高齢男性の場合、推奨量はやや減少して60gとなります。ただし体重1kg当たりの摂取量で見ると、若年層よりも多めの摂取が推奨されています。
|
年齢(歳) |
推奨量(g / 日) |
|
18~29 |
65 |
|
30~49 |
65 |
|
50~64 |
65 |
|
65~74 |
60 |
|
75以上 |
60 |
成人女性の推奨量は50g
成人女性のたんぱく質の推奨量は1日当たり50gと策定されています。これは男性の推奨量と比較すると約15g少ない数値になります。この差は女性の平均的な体格や基礎代謝率を考慮して算出されたものです。
|
年齢(歳) |
推奨量(g / 日) |
|
18~29 |
50 |
|
30~49 |
50 |
|
50~64 |
50 |
|
65~74 |
50 |
|
75以上 |
50 |
妊婦・授乳婦のたんぱく質付加量
女性の場合、妊娠や授乳中における推奨量の変化にも注目しましょう。妊娠中は胎児の健全な発育をサポートするため、授乳中は栄養価の高い母乳を生成するために、たんぱく質の重要性が一層高まります。このような時期には、通常よりも多めのたんぱく質摂取が推奨されているのです。
| ライフステージ |
推奨量(g / 日) |
|
妊婦 初期 |
+0 |
|
妊婦 中期 |
+5 |
|
妊婦 後期 |
+25 |
|
授乳婦 |
+20 |
*出典:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」 【1日の推奨量(mg)】 食品 ※ たんぱく質含有量 男性推奨量65gに必要な量 女性推奨量50gに必要な量 鶏むね肉 38.8g 約168g 約129g ゆで卵 12.5g 約10個 約8個 木綿豆腐 7.0g 約3丁 約2.5丁 焼き鮭 29.1g 約3切れ 約2.5切れ 糸引き納豆 16.5g 約10パック 約8パック
※ゆで卵1個 約50g、木綿豆腐1丁 約300g、焼き魚1切れ 約80g、糸引き納豆1パック 約40g 1日に必要なたんぱく質量を摂取するのは、難しく感じるかもしれません。しかし、日々の食事で意識して食材を選ぶことで、無理なく推奨量に到達することができます。バランスの良い献立を心がけることが、継続的なたんぱく質摂取のポイントとなるでしょう。 献立 たんぱく質量 朝食 ・ 食パン1枚(6枚切り) 約15g 昼食 ・ 鮭おにぎり1個 約15g 夕食 ・ ご飯 100g 約20g 合計 約50g 上記の献立で女性の場合は推奨量を満たせますが、男子の場合は、食べる量を1.3倍にすることで達成が可能です。もし3食での摂取が難しい場合は、間食を活用するのも効果的です。 ここまで、厚生労働省が策定した「日本人の食事摂取基準2025年版」のたんぱく質の推奨量を基準として解説してきました。 男性 年齢(歳) たんぱく質摂取量の 目標量 (1日の総エネルギー 摂取量の%) 1日の総エネルギー摂取量(kcal) たんぱく質摂取量の 目標量(g) 18〜29 13~20 30〜49 13~20 50〜64 14~20 65〜74 15~20 75以上 15~20 女性 年齢(歳) たんぱく質摂取量の 目標量 (1日の総エネルギー 摂取量の%) 1日の総エネルギー摂取量(kcal) たんぱく質摂取量の 目標量(g) 18〜29 13~20 30〜49 13~20 50〜64 14~20 65〜74 15~20 75以上 15~20
*出典:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」 日々の忙しさに追われていると、必要なたんぱく質をしっかり摂取するのが難しいと感じることもあるでしょう。そんなとき、食事内容を意識しながら、青汁を活用するのもひとつの方法です。「野菜とカルシウムとタンパク質がとれる青汁」は、たんぱく質だけでなく、体に必要な栄養成分を凝縮しています。 体の土台に必要な栄養素のカルシウムと大豆イソフラボン、大豆たんぱく(植物性)とホエイたんぱく(動物性)を一度に摂れます。さらに1日に不足する緑黄色野菜も摂ることができます。
2. 1日に必要なたんぱく質を食品で例えると
具体的な食品に換算すると、たんぱく質の必要量がより実感しやすくなります。
(100g当たり)
ひとつの食材だけからたんぱく質を摂取することは好ましくありません。たんぱく質は動物性たんぱく質、植物性たんぱく質の2種類にわけられ、バランス良くとることが重要です。
また、たんぱく質は体内に大量に蓄えておくことができないため、1日3食にわけて摂取するのが理想的といえるでしょう。各食事でたんぱく質を意識してとり入れる習慣をつけましょう。 3. たんぱく質を1日でしっかり摂取するための献立例
以下に、成人女性(50g)が1日に必要なたんぱく質量を3食で摂取するための献立例を示します。
食事
・ 目玉焼き1個
・ 野菜サラダ
・ 牛乳100ml
・ ほうれん草のおひたし
・ 豚汁(豚肉、豆腐入り)
・ 鶏もも肉のソテー90g
・ ひじきの煮もの
・ 野菜たっぷりみそ汁
例えばおやつタイムにプレーンヨーグルトや、お風呂上がりの牛乳などをとり入れることで、たんぱく質の摂取量を手軽に増やすことができます。
忙しい日常のなかでも、少しの工夫で必要な栄養素をしっかり摂取しましょう。 4. 食習慣のなかで日々のたんぱく質摂取を意識しよう

たんぱく質は私たちの健康維持に欠かせない栄養素です。1日に必要な摂取量は性別や年齢によって異なり、一般的に成人男性では約65g、成人女性では約50gが推奨量とされています。この数値を意識するだけでも、食習慣は大きく変わるかもしれません。
個人差を考慮することも重要です。体格の違いや日常の運動量によって必要なたんぱく質量は変動します。特にアスリートや筋力トレーニングを行う方は、より多くのたんぱく質が必要です。
なお、たんぱく質は体内に長期保存できないため、朝・昼・夕の3食にわけて摂取するのが理想的です。普段の料理に豆腐や納豆を加えたり、間食にヨーグルトを選んだりするなど、小さな工夫で必要量に近づけることができます。5.もうひとつのたんぱく質摂取量の指標「目標量」
実は、厚生労働省はもうひとつ、たんぱく質の必要量の指標を策定しています。策定した推奨量では、「必要量を過小に見積もっているかもしれない」という危惧があるためです。
この事を踏まえ、生活習慣や加齢による変化への対策として、「目標量」が策定されています。「たんぱく質摂取量の目標量が、「1日の総エネルギー摂取量(kcal)の%」の値として示されています。「1日の総エネルギー摂取量(ふつう)」の値を元に計算した「たんぱく質摂取量の目標量(g)」の値を下の表に示しました。
なお、50歳以上では活動量の減少や筋肉量の低下を防ぐために、目標量の下限が18~49歳の13%から、14%あるいは15%に引き上げられています。
身体活動レベルは「ふつう」
カッコ内の数値は中央値
2600
85~130(108)
2750
90~138(114)
2650
93~133(113)
2350
88~118(103)
2250
85~113(99)
身体活動レベルは「ふつう」
カッコ内の数値は中央値
1950
64~98(81)
2050
67~103(85)
1950
69~98(84)
1850
70~93(82)
1750
66~88(77)
「たんぱく質摂取量の目標量(g)」の中央値は、先に示した推奨量と比べてみると、男女ともかなり大きな数値となっています。
加齢による筋肉量の低下や身体能力の低下の対策として、ここに示した目標量の中央値程度のたんぱく質をとることを薦めます。
しかし、たんぱく質を含む食品をただ多く摂取すれば良いというわけではありません。体重1 kg当たり2 g/日以上のたんぱく質の習慣的な摂取は避けましょう。たんぱく質の習慣的な過剰摂取は、腎臓の機能を低下させます。
繰り返しですが、必要とするたんぱく質の量は個人の活動量や体格、健康状態などにより異なります。例えば、日常的にランニングや筋力トレーニングを行うなど活動量の多い人は、より多くのたんぱく質を必要とします。自分に必要な適切なたんぱく質量を知り、他の栄養素とのことも考えて、さまざまな食品からとり入れ、食生活を楽しみましょう。
忙しい毎日でも手軽に必要な栄養素を摂取!
青汁もとり入れて効率良くたんぱく質補給
この青汁の特徴は、植物性の大豆たんぱくと動物性のホエイたんぱくをダブルで配合していることです。さらに、カルシウムや大豆イソフラボンなど、体の基礎となる栄養素も同時に補えるのが魅力です。国内産ケールをはじめとする緑黄色野菜も使用されており、栄養バランスにも配慮されています。
まろやかな豆乳ミックス味で飲みやすく、わずか80mlの水に1スティックを溶かすだけという手軽さも大きなメリットです。牛乳や豆乳、果汁などに混ぜるアレンジも可能なので、毎日飽きずに続けられるでしょう。忙しい現代人のたんぱく質摂取をサポートする、頼もしい味方といえます。 野菜とカルシウムとタンパク質がとれる青汁
30本入り4,200円(税込)
手軽に続けられ、成分と飲みやすさにこだわった青汁です。





