
女性ホルモンの役割とは?年齢による変化の特徴や上手に付き合う方法も解説
女性ホルモンの役割と年齢による変化を徹底解説します。エストロゲンとプロゲステロンが月経周期や心身に与える影響から、思春期・性成熟期・更年期・老年期の特徴まで詳しく見ていきましょう。
女性ホルモンは、女性の一生を通じて心身に大きな影響を与えます。月経前のイライラや更年期の体調不良など、「なんとなく調子が悪い」と感じる原因は、女性ホルモンの変化にあるかもしれません。
エストロゲンとプロゲステロンという2つのホルモンがどのような役割を果たし、年齢とともにどう変化するのかを理解することで、自分の身体をより深く知ることができます。
本記事では、女性ホルモンの基本知識から年代別の特徴、日常でできるケア方法まで詳しく解説します。
1.ホルモンの基本的な役割や仕組み

ホルモンとは、私たちの体内でつくられる特殊な化学物質で、血液を通じて全身に運ばれながら、さまざまな臓器や細胞の働きを調整する重要な役割を担っています。
思春期になると、脳の奥深くにある下垂体という部分から特別な指令が出され、男性では精巣、女性では卵巣からそれぞれの性ホルモンが分泌されるようになります。これらのホルモンが血液に乗って体全体にいきわたることで、男性らしさや女性らしさといった身体的特徴があらわれるのです。
ホルモンの存在は普段あまり意識されることがありませんが、身体の健康を陰で支える存在です。バランスがくずれて初めて体調の変化としてあらわれるため、日頃から自分の身体の状態に注意を向けることが大切です。
2. 2つの女性ホルモンの種類と具体的な働き

女性ホルモンには「エストロゲン(卵胞ホルモン)」と「プロゲステロン(黄体ホルモン)」の2種類があり、それぞれ異なる役割を担っています。これらのホルモンは月経周期や排卵の調整にかかわるだけでなく、女性の身体や心の健康に幅広い影響を及ぼしています。
2つのホルモンの役割を見ていきましょう。
エストロゲン(卵胞ホルモン)の役割
エストロゲンは卵胞から分泌されることから「卵胞ホルモン」とも呼ばれ、女性らしい身体づくりと健康維持において中心的な役割を果たしています。
思春期には乳房の成長や丸みを帯びた体型の形成を促し、女性特有の身体的特徴をつくり出します。妊娠に向けては、子宮内膜を厚くして受精卵が着床しやすい環境を整える働きを担っているのです。
また、肌の水分量を保ち、皮脂の分泌を適切にコントロールすることで、ツヤとハリのある美しい肌を維持する役割もあります。さらに、骨量の維持や血中コレステロール値の調整、自律神経の安定化なども担うため、女性の身体を総合的に守る存在といえるでしょう。
更年期以降にエストロゲンが減少すると、さまざまな体調の変化が生じやすくなるのが特徴です。
プロゲステロン(黄体ホルモン)の役割
プロゲステロンは排卵後に卵胞が黄体に変化する際に分泌されることから「黄体ホルモン」とも呼ばれ、主に妊娠の成立と維持に深くかかわるホルモンです。エストロゲンによって準備された子宮内膜を、受精卵がより着床しやすい状態に調整する重要な働きを担っています。
身体機能への影響として、基礎体温を押し上げる作用があり、これによって排卵後の高温期が形成されます。また、将来の授乳に向けて乳腺組織の成長を促進する役割も果たしているのです。
体内に水分や栄養を蓄えやすくする性質があるため、月経前には体重増加やむくみが生じやすくなります。さらに、食欲の増加や眠気を引き起こすほか、情緒面では不安定になりやすく、月経前のイライラや気分の落ち込みの原因となることも珍しくありません。
妊娠が成立しなかった場合、排卵から約2週間後に分泌が停止し、不要になった子宮内膜が剥がれ落ちて月経が始まります。
3.【年代別】ライフステージ別に見る女性ホルモンの特徴
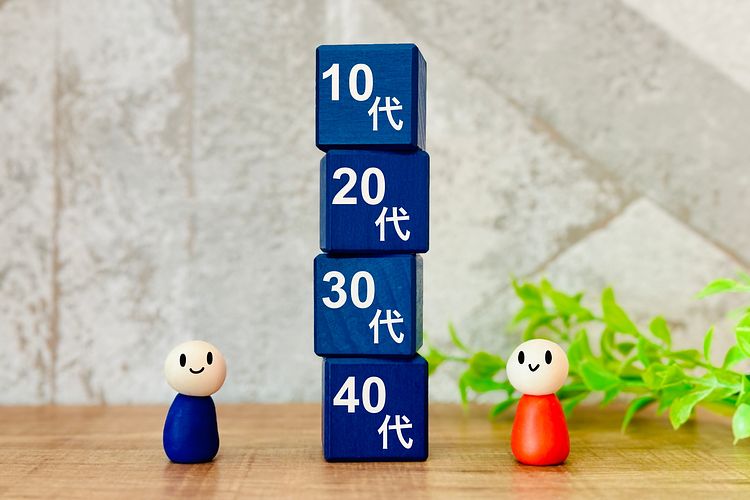
女性ホルモンの分泌量は年齢とともに大きく変化し、それぞれのライフステージで女性の心身に異なる影響を与えます。思春期から老年期まで、各時期の特徴を理解しましょう。
思春期(8~18歳頃)
思春期は子どもから大人へと成長する移行期間で、8歳頃から18歳頃までの時期です。この時期に脳の奥にある下垂体から性腺刺激ホルモンが分泌され始め、卵巣から女性ホルモンであるエストロゲンとプロゲステロンの分泌が開始されます。
女性ホルモンの影響により、乳房の発達や体脂肪の増加による丸みを帯びた女性らしい身体つきへの変化が見られるのが特徴です。また、子宮や卵巣などの生殖器官が成熟し、やがて初潮を迎えます。
ただし、思春期の発来直後は女性ホルモンの分泌が不安定なため、月経周期が不規則になったり、無排卵の状態が続いたりすることもあります。
性成熟期(18~45歳頃)
性成熟期は10代の終わりから40代前半の時期で、前期(18~37歳頃)と後期(37~45歳頃)の2つにわけられます。
前期は月経周期が安定し、ホルモンバランスが良好で妊娠・出産に最も適した時期です。特に25~30代半ばは、子宮や卵巣の機能が最も活発で、心身ともに元気な妊娠適齢期とされています。
しかし、女性の卵子は新しくつくられることがなく、年齢とともに数も質も低下していくのが特徴です。35歳前後から徐々に妊娠する力が下がり始め、40歳を過ぎると自然妊娠の確率は徐々に低下します。
後期では女性ホルモンの分泌量が少しずつ低下し、それに伴い不妊や身体の不調も増加します。
性成熟期は月経に伴うPMS(月経前症候群)や月経困難症などのさまざまな不調が起きやすく、仕事や日常生活に支障をきたすこともあるでしょう。
更年期(45~55歳頃)
更年期は閉経前後約5年ずつの計10年間を指し、日本人の平均閉経年齢が50.5歳のため、一般的には45~55歳頃に当たります。この時期は、卵巣機能の低下により女性ホルモンであるエストロゲンが大きくゆらぎながら減少していくのが特徴です。
エストロゲンの減少により、月経周期の乱れや機能性出血などの月経異常があらわれ、顔のほてりや頭痛・肩肩こり、疲労感などの多様な健康悩みが生じます。また、汗をかきやすい、手足の冷え、イライラ、睡眠の質の低下などもあらわれます。
健康悩みの程度は個人差が大きく、ホルモンの変化だけでなく、本人の性格や体質、仕事や子育て、介護などの環境的ストレスも影響しています。
老年期(55歳頃~)
閉経以降、エストロゲン不足状態が長期間続くことで、これまでホルモンによって守られていた身体機能に大きな変化があらわれます。腟粘膜の萎縮により不快感や性交痛が生じ、排尿悩みもあらわれやすくなるのが特徴です。
この時期は、エストロゲンの減少により、骨にも影響が出ると考えられています。また、皮下のコラーゲン量の減少により肌のうるおいが失われ、シミやシワが増えてくるのも特徴です。
4.女性ホルモンと上手に付き合う方法
女性ホルモンのバランスと向き合うためには、日常生活の見直しが重要です。
まず、1日3食を決まった時間の規則正しい食生活を心がけ、炭水化物・たんぱく質・脂質・ビタミン・ミネラルの5大栄養素をバランスよくとり入れることが大切です。主食・主菜・副菜のそろった食事を意識しましょう。
ほかにも、適度な運動も欠かせません。特に閉経後は筋肉量が減少しやすいため、歩幅を広くした早歩きやスクワットなどの筋力トレーニングが効果的です。階段を使う、テキパキ動くなど、日常生活にとり入れやすい身体活動から始めてみましょう。
また、ストレスは女性ホルモンのバランスを乱す大きな要因となるため、上手に解消する方法を身につけることも重要です。質の良い睡眠と適切な休養も、ゆらぐホルモンバランスをサポートする基本的な要素です。
5.まとめ
女性ホルモンは女性の一生を通じて心身の健康に深くかかわる重要な存在です。エストロゲンとプロゲステロンの2つのホルモンが、思春期から老年期まで各ライフステージでそれぞれの役割を果たし、月経周期とともに絶えず変化しています。
年齢による女性ホルモンの変化は自然な現象ですが、規則正しい食生活、適度な運動、質の良い睡眠、ストレス管理といった日常のセルフケアで、ホルモンバランスのゆらぎと上手に付き合いましょう。
まずは今日から、1日3食をバランスよくとる、階段を使う、早めに就寝するなど、できることから始めてみましょう。
*専門家が、特定の商品を推奨しているわけではありません。 更年期以降、エストロゲンの減少とともに女性の骨量は急激に低下していきます。そんな女性の骨の健康をサポートするのが大豆イソフラボンです。 女性の骨量が50歳前後から減ってゆく原因の一つは、ホルモンバランスの変化。ファンケルでは、カルシウム補給だけではない"大人の女性の骨の健康"に役立つ設計を究めました。骨の変化は自覚しづらいため、早めのケアがおすすめです。機能性関与成分大豆イソフラボンのほか、カルシウムやビタミンDも配合しています。 【届出表示】 *本品は特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。
大豆イソフラボン配合の「健骨サポート」で骨の健康をサポート
大豆イソフラボンは、骨の健康維持に役立つことが期待されています。
ファンケルの「健骨サポート」は、機能性関与成分として大豆イソフラボン25mgを配合し、さらにカルシウム400mgとビタミンD1.65μgもプラス。
1日当たり約77円で手軽に続けられる骨ケア習慣です。骨の変化は自覚しづらいため、健康悩みがあらわれる前からの早めのケアが大切です。将来の自分のために、今から骨の健康を意識した生活を始めてみませんか。健骨サポート<機能性表示食品>
30日分2,300円(税込)
本品には大豆イソフラボンが含まれます。大豆イソフラボンは、骨成分の維持に役立つ機能があることが報告されています。本品は更年期以降も骨を丈夫に維持したい女性に適した食品です。
*疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。
*食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。





