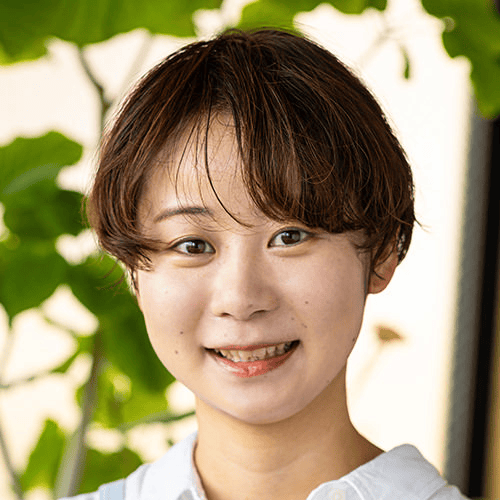子どもの偏食が心配...7つの原因と対処法をご紹介
子育てをするうえでよく聞くのが「子どもがご飯を食べたがらない」「偏食がすごくて食べられるものが少ない」などの食の悩みです。バランスのよい食事は健康に過ごすために欠かせないため、子どもに偏食があるとママやパパが心配するのは当然です。しかし、幼児期の偏食は過剰に心配しなくても大丈夫。今回はなぜ心配し過ぎる必要がないのか、子どもが偏食をする理由や対策方法について解説します。
1. 子どもの偏食は当たり前?
子どもの偏食はママやパパの心配の種だと思いますが、子どもの偏食は当たり前に起こることだと考えましょう。そもそも偏食とは、特定の食品を口にしようとしない、あるいは特定の食品しか口にしないことを指します。
子どもは味覚も成長段階にあるため、食べられるものと食べられないものがあるのは当然のことなのです。しかし、体の成長とともに味覚も発達し、食べられるものの種類は増加する傾向にあります。
また、経験を重ね、「これは食べても大丈夫なもの」と判断できるようになることから、徐々に偏食は解消されるでしょう。
2. 偏食の原因で考えられること7つ

そもそもなぜ子どもは偏食しやすいのでしょうか。ここでは主に考えられる7つの原因をご紹介します。ただし、偏食はどれかひとつが原因となるのではなく、さまざまな要因が絡んでいることが多いことも覚えておきましょう。
味や食感が苦手
大人でもあることですが、味や食感が苦手な食品は避ける傾向にあります。子どもは味覚が鋭く、苦みや酸味を苦手とするケースも多々あります。人間は本能的に「苦み=毒」「酸味=腐敗」と捉えるため、経験の少ない子どもが敬遠するのも無理はありません。例えば、子どもが苦手な野菜の代表格といえば、苦味のあるピーマンやゴーヤなどが挙げられます。
また、人によって苦手な食感もあるでしょう。例えば、カボチャやサツマイモはパサつく食感です。口の中の水分が奪われて飲み込みにくい、といった経験をすると、それ以降避けることもあるでしょう。
見た目が苦手
偏食の理由のひとつに、見た目があります。例えば、魚の切り身は平気なのに姿焼きだと食べられないケースは、魚の目が怖いと感じることもあるようです。苦手ではない人から見ると「そんな理由?」と思うかもしれませんが、苦手な子どもにとっては、食べられない理由になるのです。
においが苦手
味はおいしくても、においが苦手で食べられないこともあります。例えば、納豆をおいしく食べられる人はにおいも気になりませんが、苦手な人にとっては発酵したにおいを不快と捉えてしまう場合もあります。人にはそれぞれ受け入れられるにおいと、そうでないにおいがあるのです。
はじめて食べる食材だから
子どもは新しく見る食材ばかりで、食べてもいいものかどうか判断がつきません。例えば、初めてこんにゃくを食べたとき、黒っぽい見た目とグニャグニャした食感に驚き、苦手意識を持つこともあります。経験を重ねるうちに「これはおいしいもの」「食べられるもの」とインプットしますが、そうでないうちはどうしても苦手意識が上回ってしまいます。
食材に対してのトラウマがある
魚の骨が喉に刺さると、怖くて食べられなくなるように、食材に対して何らかのトラウマを抱えることもあります。「うどんを食べたときに熱くてやけどをした」、「牛乳を飲んだらおなかが痛くなった」などの経験がトラウマとなって、その食材を食べることを拒否してしまうケースは少なくありません。
食べることに興味がない
子どもによっては、そもそも食べることに興味がないケースもあります。「食べるより遊んでいたい」「食が細く、食に楽しさを見いだせない」など、理由はさまざまです。明確な理由がないのに偏食がある場合は、今の段階では食べることに興味がないのかもしれません。
食器類を上手に扱えない
幼児食以降、手づかみからスプーンなどの食具に移行し、食器も自分で持って食べなくてはなりません。食具や食器類を上手く扱えないと、中々口に運べず、食に対して苦手意識を抱く可能性があります。特に手先が不器用な子どもは年相応の動作ができないこともあり、食べることに苦痛を感じているかもしれません。
3. 子どもの偏食にはどんな対策ができる?
子どもの偏食で考えられる原因をお伝えしましたが「成長するまで偏食はしょうがない」と割り切れないのが親心ですよね。少しでも食べられるものを増やして、健康に育ってほしいもの。では、子どもの偏食にはどんな対策ができるのでしょうか。
偏食の原因を聞く
自分の気持ちが伝えられる年齢であれば、親があれこれ考えるよりも、まずは子どもに偏食の理由を聞いてみましょう。「どうして、○○○が嫌いなの?」「○○○ばかり食べるのは、どうして?」など、理由を聞いてみると傾向や対策方法が見えてくるかもしれません。そのうえで、以下でご紹介する対策をするとよいでしょう。
なるべく舌触りや食感が良くなる工夫をする

苦手な食材でも、調理方法を変えることで食べられるようになることがあります。例えば、とろろのドロドロとした舌触りが苦手であれば、すりおろさず、角切りやせん切りにするだけでも舌触りが変わります。
また、ごぼうのような硬い食感が苦手であれば、ポタージュにするとなめらかな食感になり「硬いから苦手」という課題をクリアできます。そのほかにも食感を変えるために、細かく刻む、柔らかくなるまで煮る、揚げてサクサクにするなども有効的な手段です。
以上のように舌触りや食感を変えることで、食べられる方法がないか試してみましょう。
いつもの味付けから変えてみる
子どもが食べてくれないと、半ば諦めて同じような味付けにしていませんか。例えば、さばが苦手だとしましょう。いつもは塩焼きのところを「さばの竜田揚げ」「さばのみそ煮」「さばカレー」など別の料理にしてみると、案外食べてくれることがあります。苦手な理由のひとつに、同じ味で飽きてしまうからというケースもあるため、いつもと違った味付けを試してみるのもよいでしょう。
一緒に買い物や料理をする

子どもと一緒に買い物に行ったり、料理をしたりするのも、偏食解消に有効な手段です。例えば、普段は野菜が苦手でも、自分で育てたものなら食べられるという話を聞いたことがありませんか。その感覚を日常生活で子どもに感じてもらうことで、おいしく食べられるようになるはずです。
一緒に買い物に行けば、調理前の形を見られるので「何か分からなくて苦手」という意識を払しょくできるかもしれません。また、一緒に料理をつくることで、その達成感から食べてみたいという興味がわきやすくなります。
おやつをあげすぎない
おやつは食事で補いきれなかった栄養やエネルギーを補給するために大切なものですが、あげすぎは禁物です。おやつの食べすぎでおなかがいっぱいになり、食事が摂れなくなることもあります。
また、おやつをダラダラと長時間食べさせることも控えましょう。あげる時間と量を決め、食事に響かないよう配慮することが大切です。
子どものおやつは、以下を目安にしてください。
・1~2歳児:150kcal(例:ヨーグルト+果物、小さなおにぎり)
・3~5歳児:200~250kcal(例:おにぎり+果物+小魚)
参照:幼児期のおやつは何をどのくらい食べたらいいの? | 母子栄養協会
おいしそうに食べる姿を見せる

皆さんは、グルメ番組やSNSのグルメ投稿を見ていると、食欲がわいた経験はありませんか。一般的に誰かがおいしそうに食べている姿を見ると、自然と興味をそそられるため、そうした番組や投稿などが昔から人気があるのです。
子どもは食の経験が浅く、初めて口にする食べ物が多いため、食べることに不安が生じることがあります。そこで率先して大人がおいしそうに食べていると「これはおいしい食べ物なんだ」と興味を持つようになります。
さらに、誰かと会話しながら楽しい雰囲気の食卓にすることで、より食事をおいしく感じることができるでしょう。
生活リズムを整える
子どもが食事を摂りたがらない理由のひとつに、生活リズムの乱れがあります。夜遅く寝て、朝も遅くに起きる生活習慣が身に付いていると、朝食を食べたがらないでしょう。
十分に朝食を食べない状態では、昼食前におなかが空き、おやつを食べてしまうことで、昼食はおなかが空いていないから食べられない、といった悪循環に陥ります。早寝早起きの生活習慣を身につけることで、自然と適切な時間におなかが空くようになり1日3食の食事を、規則正しい時間に食べられるようになるでしょう。
サプリメントを活用する
成長段階にある子どもは、食事から栄養を摂取することが大事です。
あまりにも食べられるものが少ないと、栄養の偏りが心配されます。まずはこれまで紹介した方法で、楽しく食事をとれるように工夫をしてみましょう。
それでも、なかなか食べてもらず栄養の偏りがでてきてしまうといった場合は、子ども向けのサプリメントを利用するのもよいでしょう。子ども向けのサプリメントはおやつ感覚で食べられるものが多く、無理強いせずとも子どもが食べてくれるよう工夫されています。
4. 子どもの偏食に対してやってはいけないこと
子どもの偏食の対応として適さない方法があります。ここでご紹介する対応はついやってしまいがちですが、食に対するネガティブなイメージを増長しかねないため、控えましょう。
嘘をつかない
苦手な食材が入っているのに「入っていないから大丈夫!」など嘘をつくことがあります。少しでも食べてほしくてつい噓をついてしまいますが、これは子どもが大人に対して不信感を抱くようになる行動です。
また、苦手な食材が入っていないのに「もしかしたらまた入っているのでは......」と疑うようになってしまいます。結果として偏食がひどくなる恐れがあるため、噓をつくのはやめましょう。
食べることを強制しない
苦手な食材を口にするよう促されると嫌な気持ちになるため、強制は避けるべきです。つい「一口でいいから食べてごらん」「せっかく作ったのに......」などと声をかけてしまいがちですが、これも強制にあたります。
また、苦手なものを食べるまでずっと注目するのも、やめましょう。強制されると食べること自体が苦痛になり、ますます偏食がひどくなることもあります。食べるかどうかは子どもが決めることであり、大人ができるのはゆっくり見守ることと、楽しく食事ができるよう明るい雰囲気をつくることです。
怒らない・叱らない
ママやパパは子どものすこやかな成長のために、ついあれこれ食べるよう口を出してしまいがちです。心配や焦りがイライラにつながってしまい「なんで食べないの!?」「食べないならおやつはなしだからね!」など、怒ったり叱ったりしがちです。
しかし、子どもの偏食は怒られても治りません。むしろ「苦手な食材が出る=また怒られる」と嫌な思い出に結びつき、ますます食べたくなくなるのです。そのため、大人はゆっくり見守ることに徹しましょう。
5. まとめ
子どもの偏食の原因は、味覚の鋭さや食の経験が浅いことなどが関係するため、どの子どもにも起こって当然です。成長すると徐々に偏食も少なくなるため、成長段階のひとつと捉えておおらかに見守りましょう。ただし、パパやママが工夫することで偏食を解消するきっかけを作れることもあります。今回紹介した対策を取り入れて、無理なく楽しく食事ができるといいですね。