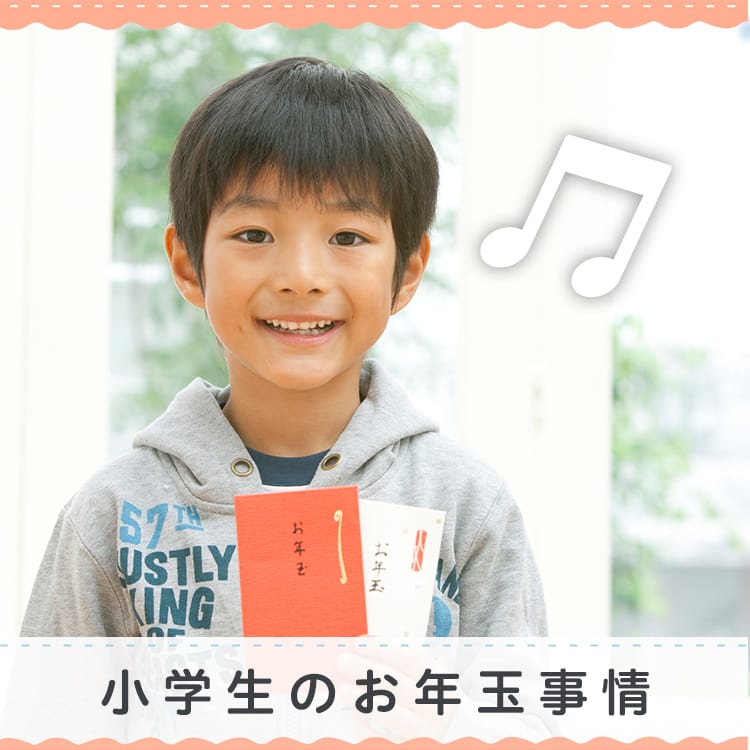
小学生のお年玉の相場はいくら? あげるときのポイントや注意点も解説
小学生にあげるお年玉はいくらくらいが適切なのか、相場が気になる人は多いでしょう。少なすぎてガッカリさせたくはないですし、渡しすぎてトラブルの元になるのも避けたいですよね。 この記事では、アンケートの結果を基に、小学生にあげるお年玉の相場を詳しく解説します。また、お年玉を渡すときのマナーや注意点、もらったお年玉の管理方法について考えるヒントもご紹介します。
1. 小学生のお年玉の相場はいくら?
住信SBIネット銀行が2020年12月に実施したインターネットアンケート(※1)によると、小学生に渡すお年玉の金額は、低学年(1~3年生)で1,001~3,000円、高学年(4~6年生)は3,001~5,000円が最も多い回答でした。それぞれ全体の4割程度を占めており、お年玉の相場として参考となるでしょう。
また、金融広報中央委員会が実施した「子どものくらしとお金に関する調査(2015年度)」(※2)によると、小学生がもらうお年玉の総額は、低学年(1、2年生)は1万円くらい、中・高学年(3~6年生)は1万円~1万9,999円が最多でした。ただし、どちらも全体の2~3割程度で、突出して高い回答ではありません。どのような関係性の大人からもらうか、何人からもらうかによって総額は幅広くばらつきます。
※1 出典:住信SBIネット銀行株式会社「お年玉に関する意識調査2021」
※2 出典:金融広報中央委員会「子どものくらしとお金に関する調査」(第3回)2015年度調査
2. 小学生にお年玉をあげるときのポイント
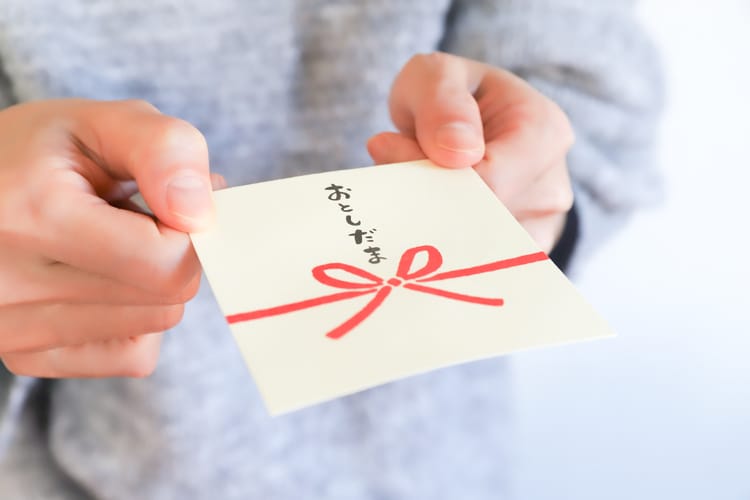
お年玉は金額も大事ですが、あげるときのマナーにも気を配りましょう。お金のやり取りに関するマナーを教える機会でもあります。また、相手の親の目にも触れるものなので、失礼がないようにしっかりと準備をしましょう。
ここでは、小学生にお年玉をあげる際に気を付けたいポイントをご紹介します。
現金をそのまま渡さない
お年玉を渡すときは、お金をそのまま渡すのではなく、ポチ袋などに入れて渡しましょう。ポチ袋の柄は何でもOKです。子どもが好きなキャラクターや色柄のものを選ぶと喜ばれたり、話の種になったりすることもあるのでおすすめです。
ポチ袋の表面には、渡す子どもの名前を、裏面には自分の名前を書きましょう。こうすることで、渡す側は相手を間違えることがなくなり、もらう側も誰からのお年玉なのかを後で確認しやすくなります。
お札は、向きを揃えて重ねてから、三つ折りにしてポチ袋に入れてください。新年という節目にふさわしい気持ちになれるよう、新札を用意できればベターです。
縁起が良いとされる金額を渡す
ご祝儀の場合、お札の枚数を奇数で用意するのがマナーとされていますが、お年玉の場合はそこまでこだわらなくても問題ありません。末広がりの「8」も縁起の良い数字なので、金額に迷った場合は選択肢の一つに入れてみても良いでしょう。
避けるべき金額としては、死を連想する「4」や、苦を連想させる「9」の数字が挙げられます。新年のめでたい席で未来ある子どもに渡すお年玉にはふさわしくないため注意しましょう。
3. 小学生にお年玉をあげるときの注意点

小学生にお年玉をあげるときは、相手の親などに負担をかけないように渡すことが大切です。配慮が不足していると、思わぬトラブルに発展してしまう可能性もあります。ここからは、お年玉をあげるときの注意点を4つご紹介します。
大人(親)がいるときに渡す
相手の親などがいないときにお年玉をあげると、お年玉をもらったことを親に報告しなかったり、もらったお年玉を雑に扱い紛失してしまったりする恐れがあります。
お年玉は、新年を祝うために子どもにお金を贈るという面だけでなく、家と家とのお金のやり取りという側面も持つものです。そのため、お年玉は必ず親の目がある場所で渡し、いつ・誰に・いくらもらったのかを先方の家庭が正確に把握できるようにしましょう。
各家庭の教育方針に合わせる
自分の子ども以外にお年玉を渡す場合は、相手の家庭の方針とズレが生じないか、ひと言相談するのがベストです。「お小遣いを渡していないので直接お金を渡すのはまだ早い」「大きすぎる金額は避けてほしい」など、家庭ごとにお金の扱いや考えは異なります。相場や自分の考える常識だけにとらわれないよう気を付けましょう。
親戚間でお年玉の金額について決めておく
親同士が兄弟姉妹など家と家の間でお年玉を渡し合うときは、渡す金額ともらう金額に大きな差が出てしまわないよう、事前に話し合っておくと安心です。家庭ごとに子どもの人数が異なる場合は、渡す金額を揃えるのか、総額を合わせるのかも決めておきましょう。
お年玉のやりとりは何年も続くことが多いため、ちょっとした不満が積もり積もって思わぬトラブルへ発展してしまうこともあります。金額を合わせるのが難しい場合は、手土産をプラスするなどの気遣いをするのも良いでしょう。
電子マネーで渡す際は事前に確認する
最近では、〇〇Pay、〇〇ペイといったモバイル決済を利用して、電子マネーでお年玉を渡す方法もあります。「直接会えなくてもお年玉を渡せる」「もらった金額が履歴で明確化される」といった点が、他の渡し方にはない大きなメリットです。
ただし、「お金の大切さが伝わりにくい」「味気がない」など、相手の親にマナー違反と思われることもあります。使える場所が制限される不便さや、逆に子どもが自由に使えてしまうことへの心配も考えられるため、事前に相手の親に確認をしましょう。
4. 子どものお年玉ってどんなふうに管理するべき?

もらったお年玉で子どもがほしいものを買うだけでなく、子どもの将来に向けて貯金するという家庭も珍しくありません。
実際、どのようにお年玉を管理(保管、活用)している家庭が多いのか、住信SBIネット銀行が2020年12月に実施したインターネットアンケート(※)の結果などを参考に見ていきましょう。
※ 出典:住信SBIネット銀行株式会社「お年玉に関する意識調査2021」
銀行預金
住信SBIネット銀行のアンケート調査では、7割を超える親が子どものお年玉を円普通預金で管理しています。一方で、子どもを対象にした調査(※)では、預金や貯金をすると回答した小学生の割合は5割弱に留まりました。
「自分(子ども本人)の貯蓄があるようだが家の人が管理しているのでよく分からない」と回答している子どもが2~3割ほどいることから、親子間で預貯金の情報共有が不足しているケースもあることが分かります。
お年玉を銀行へ預けるときは、子どもが自分事として認識できるよう、口座開設や記帳を親子一緒に行なうと良いでしょう。
※ 出典:金融広報中央委員会「子どものくらしとお金に関する調査」(第3回)2015年度調査
現金保管
お年玉を現金のまま保管していると回答した親は全体の2割前後でした。複数回答ができるアンケートのため、全額ではなく一部だけを現金で手元に置いておくケースも多いと考えられます。
子どもの年齢や興味に合わせ、ある程度は自由にお金を使う経験も必要です。蓄えておきたいと考える大人の意識と子どもの気持ちとの折り合いが付けられるよう、お金の使い道や額について親子で話し合ってみてください。
学資保険
お年玉の管理方法として、学資保険もあります。アンケート調査では、管理方法として学資保険を選んだ人が、2020年が3.5%、2021年は2.4%となっています。
学資保険は、子どもの教育資金の準備を目的とした貯蓄型の保険です。万が一のことがあっても教育資金を確保できることや、受け取るタイミングが選べたり、所得控除の対象となるため、子どもの将来を見据えて選択する人もいるようです。
その他投資
お年玉を投資に活用する家庭も増えているようです。アンケート結果を見てみると、2020年は投資信託が3.8%、株が3%の割合でしたが、2021年になると投資信託が9%、株は6.4%といずれも倍以上に増えていました。
少額でも、自分のお金で行なう投資経験は、子どもの将来に必ず役に立ちます。運用状況を親子でときどきチェックすることで、投資したお金がなぜ増えたのか(減ったのか)、どのニュースと関係していたのかなど、年齢に応じて社会への関心を持たせることもできるでしょう。
5. まとめ
小学生に渡すお年玉の相場金額は年齢によっても異なりますが、おおむね1,000円~5,000円という結果でした。渡し方のマナーや注意点にも気を配り、お年玉という習慣を、1年のスタートにふさわしい、楽しく喜ばしい出来事の一つにしましょう。
また、お年玉をはじめ子どものお金の管理方法について家庭内でよく話し合い、現状をときどき情報共有することが大切です。お金に関する意識、金融リテラシーを高める第一歩にもなります。
この記事を参考に、トラブルなくスムーズにお年玉を渡せるよう準備しておきましょう。





