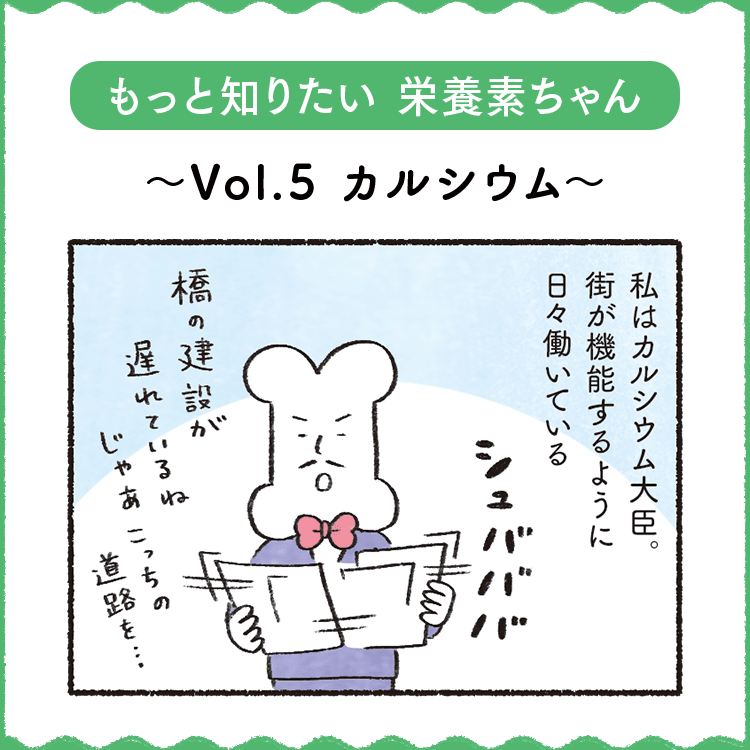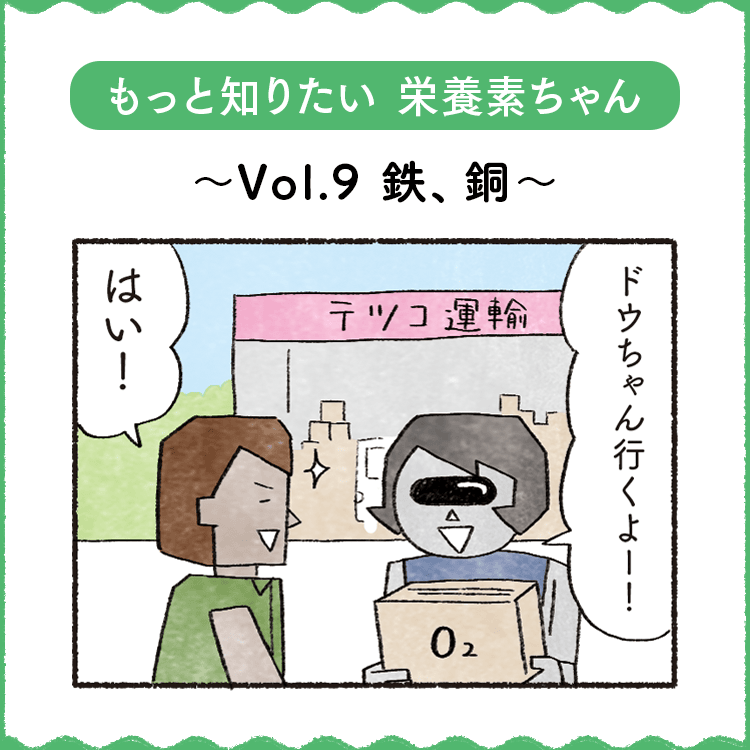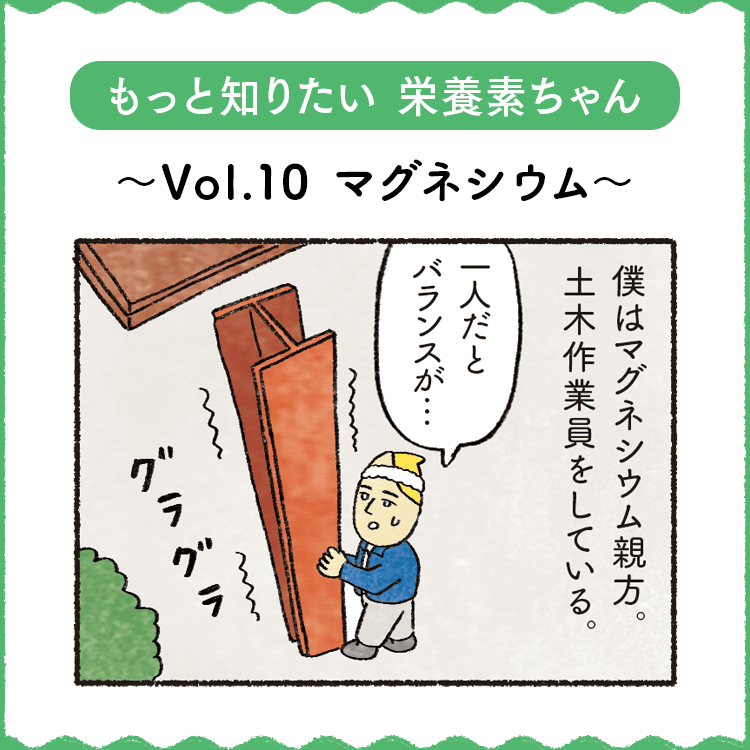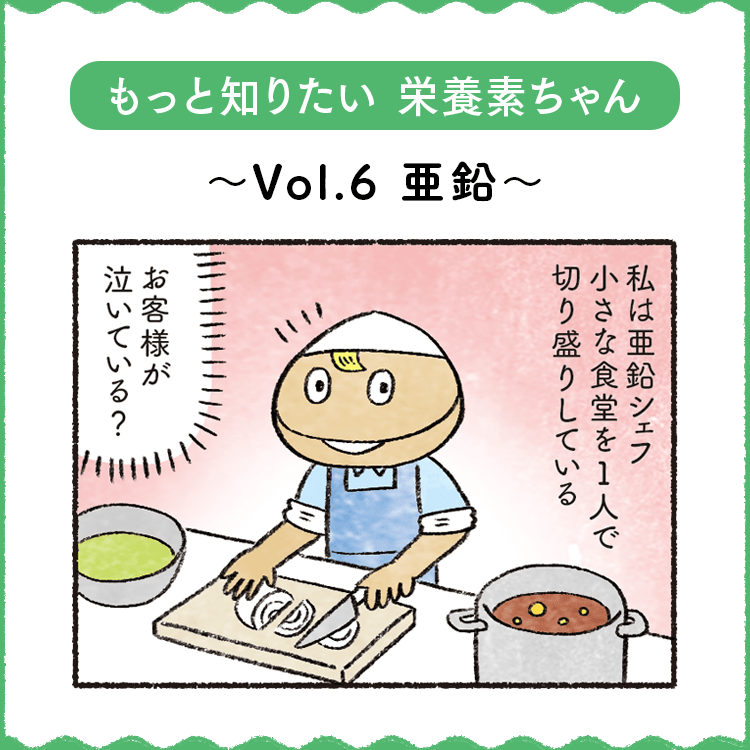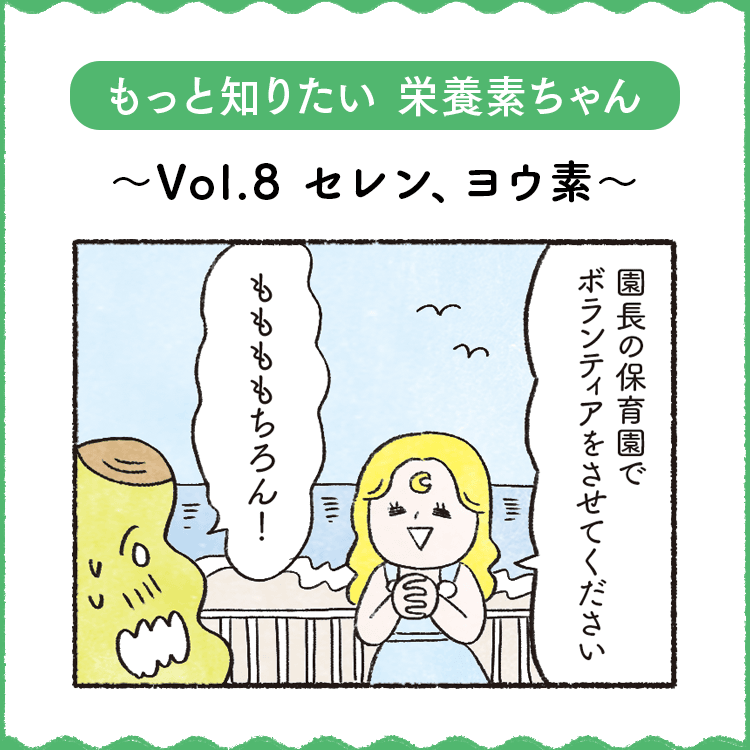ミネラルの種類と豊富に含まれる食材は? 効率よく摂る方法も解説
体の調子を保つために欠かせないミネラル。多くの種類があるため、どのミネラルがどのような働きをするのか、どのくらい必要なのか、意外と知らないことが多いものです。
そこで、この記事ではミネラルの種類や働き、豊富に含まれている食材などをご紹介。またサプリメントでミネラルを摂る場合のポイントや選び方も解説します。
1. ミネラルの種類と働き
ミネラルは体の調子を整える重要な栄養素で、骨などの体の組織を構成し、筋肉や神経の働きを調節してくれます。
しかし体内ではつくれないため、サプリメントなどでバランスよく摂取することが大切です。今回は厚生労働省が摂取基準を定めるミネラルのうち、以下の7種類をご紹介します。
・カルシウム
・鉄
・マグネシウム
・銅
・亜鉛
・マンガン
・セレン
カルシウム
カルシウムは、丈夫な歯や骨をつくるために欠かせないミネラル。体内に最も多く存在するミネラルで、そのほとんどが骨や歯に存在しています。不足すると骨がもろくなり、骨粗しょう症の原因に。体に吸収されにくい性質があり、日本人は摂取量が不足しがちです。ビタミンDと一緒に摂ると吸収率がアップします。
鉄
鉄は血液をつくるために必要なミネラル。赤血球のヘモグロビンの材料となり、体内に取り込まれた酸素を全身に運ぶ働きがあります。
マグネシウム
マグネシウムは約300種類ある食べ物の消化や吸収、代謝など体の中で起こる化学反応を促進する酵素の働きを助ける作用があるミネラルです。また、筋肉の収縮を促したり、血液循環を保ったりする働きもあります。
銅
銅は鉄が赤血球の材料になるのを助けるミネラル。丈夫な骨をつくるのにも欠かせない栄養素です。鉄が十分あっても銅がないと赤血球をうまくつくれないため、銅の不足も貧血の原因になります。
亜鉛
亜鉛は味覚を正常に保ち、皮膚や粘膜の再生を促すのを助けるミネラル。新しい細胞がつくられるときに必要な栄養素です。
マンガン
マンガンは、骨の形成やエネルギーの代謝に関わるミネラル。三大栄養素である糖質・脂質・たんぱく質の代謝をサポートする酵素の構成成分であり、成長や生殖にも関係しています。穀類や豆類、茶葉などの植物性食品に多く含まれているのが特徴です。
セレン
セレンは、甲状腺ホルモンの代謝や抗酸化作用に欠かせないミネラル。たんぱく質と結合することで体内に吸収されやすくなり、細胞を傷つけて老化を引き起こす活性酸素の働きを抑制。肌や筋肉、血管などの老化を防ぐ働きをサポートしてくれます。
2. ミネラルが豊富な食材には何がある?
普段の食事の中で摂取しやすいミネラルもありますが、意識的に取らないと不十分になるミネラルもあります。また、体内で合成できないミネラルは、毎日バランスよく摂りたいもの。一つの食品ではなく、複数をバランスよく摂取するのがおすすめです。
ここでは、ミネラルを含む食品を理解することで、バランス良く取れるように、ミネラルを多く含む食品を紹介します。
カルシウムがとくに豊富なのは「干しえび」
丈夫な骨や歯に欠かせないカルシウム。特に多く含まれる食品は、以下のとおりです。
| 順位 | 食品 | 100g当たりの含有量(mg) |
| 1位 |
干しえび |
7,100 |
| 2位 |
がん漬け |
4,000 |
| 3位 |
焼き干し(とびうお) |
3,200 |
| 4位 |
乾燥バジル |
2,800 |
| 5位 |
田作り(かたくちいわし) |
2,500 |
出典:文部科学省「食品成分データベース」 ※「成分」リストから成分名を選択
骨や殻まで食べられる干しえびや焼き干しなどの魚介類は、カルシウムの含有量が高め。中華食材や煮干しとして気軽に入手でき、取り入れやすい食材です。その他に、ナチュラルチーズやえんどう豆でも摂取が可能です。
例えば、成人女性1日のカルシウムの目安量は650mgですが、その量を摂るのには、干しえび約10g(小袋1袋程度)を食べる必要があります。
出典:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020 年版)」
出典:文部科学省「食品成分データベース魚介類/<えび・かに類>/(えび類)/加工品/干しえび可食部10gあたりの数値/カルシウム710mg」
鉄がとくに豊富なのは「乾燥バジル」
血液をつくるために欠かせない鉄。特に多く含まれる食品は、以下のとおりです。
| 順位 | 食品 | 100g当たりの含有量(mg) |
| 1位 |
乾燥バジル |
120.0 |
| 2位 |
乾燥タイム |
110.0 |
| 3位 |
赤こんにゃく |
78.0 |
| 4位 |
乾燥青のり |
77.0 |
| 5位 |
あゆの焼き物 |
63.0 |
出典:文部科学省「食品成分データベース」 ※「成分」リストから成分名を選択
含有量が最も多いのは乾燥バジル。洋風メニューの風味付けに便利な香辛料です。しかし、これだけで1日に必要な量の鉄を摂るのは難しいです。ある程度の量を食事に取り入れやすい食品では、あさりの水煮缶(40g当たり12.0mg)がおすすめ。
例えば、成人女性1日の鉄の目安量10.5〜11mgを摂るのには、あさりの水煮缶で約40g(2/3缶程度)を食べる必要があります。
出典:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020 年版)」
出典:文部科学省「食品成分データベース/魚介類/<貝類>/あさり/缶詰/水煮可食部40gあたりの数値/鉄12.0mg」
マグネシウムがとくに豊富なのは「あおさ」
筋肉の働きに関わるマグネシウム。特に多く含まれる食品は、以下のとおりです。
| 順位 | 食品 | 100g当たりの含有量(mg) |
| 1位 |
乾燥あおさ |
3,200 |
| 2位 |
乾燥青のり |
1,400 |
| 3位 |
てんぐさ(天草) |
1,100 |
| 4位 |
乾燥わかめ |
1,000 |
| 5位 |
ひとえぐさ |
880 |
出典:文部科学省「食品成分データベース」 ※「成分」リストから成分名を選択
含有量が高いのはあおさや青のりなどの海藻類。和食のメニューに彩りや風味をプラスできる食材ですが、それだけで1日に必要な量のマグネシウムを摂るのは難しいもの。
取り入れやすい食品として、玄米といわしの丸干しがおすすめです。成人女性1日のマグネシウム目安量は270〜290mg。玄米で約180g(お茶碗1杯程度)にいわし丸干しを約100g(2尾程度)を組み合わせて食べると目安量を摂取できる計算になります。
出典:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020 年版)」
出典:文部科学省「食品成分データベース/魚介類/<魚類>/(いわし類)/まいわし/丸干し可食部100gあたりの数値/マグネシウム100mg」 / 「穀類/こめ/[水稲めし]/玄米可食部180gあたりの数値/マグネシウム200mg」
銅がとくに豊富なのは「ほたるいかのくん製」
鉄が赤血球の材料になるのを助ける銅。特に多く含まれる食品は、以下のとおりです。
| 順位 | 食品 | 100g当たりの含有量(mg) |
| 1位 |
ほたるいかのくん製 |
12.00 |
| 2位 |
ほたるいかのつくだ煮 |
6.22 |
| 3位 |
牛レバー |
5.30 |
| 4位 |
干しえび |
5.17 |
| 5位 |
ピュアココア |
3.80 |
出典:文部科学省「食品成分データベース」 ※「成分」リストから成分名を選択
含有量が高いのはほたるいかのくん製やつくだ煮です。おかずやおつまみとして食べられます。その他、取り入れやすい食品として、ココアやたこなどもあります。
成人女性1日の銅の目安量は0.7mg。を摂るには、ほたるいかのくん製であれば、約6g(2/3杯程度)食べれば1日の目安量を摂取できる計算になります。
出典:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020 年版)」
出典:文部科学省「食品成分データベース/魚介類/<いか・たこ類>/(いか類)/ほたるいか/くん製可食部6gあたりの数値/銅0.72mg」
亜鉛がとくに豊富なのは「かきの缶詰」
味覚を正常に保ち、皮膚や粘膜の再生を促すのを助ける亜鉛。特に多く含まれる食品は、以下のとおりです。
| 順位 | 食品 | 100g当たりの含有量(mg) |
| 1位 |
かきの缶詰 |
25.0 |
| 2位 |
かきの水煮 |
18.0 |
| 3位 |
小麦胚芽 |
16.0 |
| 4位 |
生かき |
14.0 |
| 5位 |
かつお塩辛 |
12.0 |
| 5位 |
カキフライ |
12.0 |
出典:文部科学省「食品成分データベース」 ※「成分」リストから成分名を選択
含有量の高さで特徴的なのがかき。缶詰や水煮、生食などは取り入れやすく、亜鉛の補給にぴったりです。成人女性1日の亜鉛の目安量8mgを摂るには、かきの缶詰で約33g(1/2缶程度)を食べる必要があります。
出典:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020 年版)」
出典:文部科学省「魚介類/<貝類>/かき/くん製油漬缶詰可食部33gあたりの数値/銅8.3mg」
マンガンがとくに豊富なのは「乾燥クローブ」
三大栄養素の代謝に関わる酵素を助けるマンガン。特に多く含まれる食品は、以下のとおりです。
| 順位 | 食品 | 100g当たりの含有量(mg) |
| 1位 |
乾燥クローブ |
93.00 |
| 2位 |
玉露茶 |
71.00 |
| 3位 |
せん茶 |
55.00 |
| 4位 |
シナモン粉末 |
41.00 |
| 5位 |
しょうが粉末 |
28.00 |
出典:文部科学省「食品成分データベース」 ※「成分」リストから成分名を選択
含有量が高いのは乾燥クローブなどの香辛料やお茶。香辛料としてメニューにプラスしたり、お茶として飲んだりできる食材です。その他、日々の食事のなかで取り入れやすいのが玄米です。
玄米で約180g(ご飯茶碗1杯程度)で、成人女性1日のマンガンの目安量3.5mgが摂れます。
出典:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020 年版)」
出典:文部科学省「食品成分データベース/穀類/こめ/[水稲めし]/玄米可食部180gあたりの数値/マンガン3.71mg」
セレンがとくに豊富なのは「かつお節」
抗酸化作用で老化予防を助けるセレン。特に多く含まれる食品は、以下のとおりです。
| 順位 | 食品 | 100g当たりの含有量(μg) |
| 1位 |
かつお節 |
320 |
| 2位 |
粉からし |
290 |
| 3位 |
かつお裸節 |
240 |
| 3位 |
豚の腎臓(生) |
240 |
| 5位 |
牛の腎臓(生) |
210 |
出典:文部科学省「食品成分データベース」 ※「成分」リストから成分名を選択
含有量が最も高いのはかつお節。棒状のかつお節で、削って出汁を取ればみそ汁や和食がぐっとおいしくなります。しかし、これだけで1日に必要な量のセレンを摂るのは難しいもの。普段の食事に取り入れやすいのが、秋ガツオです。
成人女性1日のセレンの目安量は25μgですが、秋ガツオで約25g(刺身大1切れ程度)を食べれば1日の目安量が摂れます。カツオ以外にも、トビウオやイワシからも摂取が可能です。
出典:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020 年版)」
出典:文部科学省「食品成分データベース/魚介類/<魚類>/(かつお類)/かつお/秋獲り/生可食部25gあたりの数値/セレン25μg」
クロムがとくに豊富なのは「あおさ」
糖質や脂質の代謝を高める働きが期待できるクロム。特に多く含まれる食品は、以下のとおりです。
| 順位 | 食品 | 100g当たりの含有量(μg) |
| 1位 |
乾燥あおさ |
160 |
| 2位 |
冷凍アサイー(無糖) |
60 |
| 3位 |
乾燥バジル |
47 |
| 4位 |
乾燥青のり |
39 |
| 4位 |
粉寒天 |
39 |
出典:文部科学省「食品成分データベース」 ※「成分」リストから成分名を選択
含有量が最も高いのは乾燥あおさなどの海藻類や、乾燥バジルといった香辛料。みそ汁の具やメニューの風味付けに活用しやすい食品です。その他に、焼きのりや昆布、わかめといった海藻類にも含まれています。
成人女性1日のクロムの目安量は10μgのため、乾燥あおさであれば10g食べれば摂取できる計算になります。普段の食事に取り入れやすい食材としては、じゃがいもがあります。じゃがいも約250g(中2個程度)を食べれば、目安量の10μgが摂れます。
出典:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020 年版)」
出典:文部科学省「食品成分データベース/いも及びでん粉類/<いも類>/じゃがいも/塊茎/皮なし/生可食部250gあたりの数値/クロム10μg」
モリブデンがとくに豊富なのは「いり大豆・青大豆」
肝臓や腎臓に存在し、酵素の働きを助けるモリブデン。特に多く含まれる食品は、以下のとおりです。
| 順位 | 食品 | 100g当たりの含有量(μg) |
| 1位 |
いり大豆・青大豆 |
800 |
| 2位 |
黄大豆(乾燥) |
660 |
| 3位 |
黒大豆(乾燥) |
570 |
| 4位 |
やぶまめ(乾燥) |
460 |
| 5位 |
青きな粉 |
450 |
| 5位 |
青大豆(乾燥) |
450 |
出典:文部科学省「食品成分データベース」 ※「成分」リストから成分名を選択
モリブデンの含有量が高いのは豆類。どれもスーパーなどで気軽に手に入れることができ、料理にも使いやすい食材です。
例えば、成人女性1日のモリブデンの目安量は25μgですが、摂るにはいり大豆・青大豆を約3g(9粒程度)を食べる必要があります。
出典:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020 年版)」
出典:文部科学省「食品成分データベース/豆類/だいず/[全粒・全粒製品]/いり大豆/青大豆可食部3gあたりの数値/モリブデン24μg」
3. ミネラルを効率よく摂るには?
各種ミネラルを効率よく摂るには、栄養バランスの取れた食事が大切です。主食、主菜、副菜をバランスよく摂るのが理想的。外食が多くなりがちな人も、さまざまな食材や栄養を摂れるメニューを選べると安心でしょう。
また、栄養バランスが不安なときは、栄養を手軽に補給できる青汁やサプリメントを活用するのもおすすめ。仕事や家事、育児、介護で忙しい人にもぴったりです。
4. ミネラルサプリの選び方をチェック!
ミネラルサプリはたくさんの種類があり、どれを選んでいいか迷ってしまうもの。ここでは、ミネラルサプリを選ぶポイントをご紹介します。自分に合ったサプリメント選びにお役立てください。
ミネラルの配合バランスはどうか
どんなミネラルが、どのようなバランスで配合されているかを確認しましょう。例えば以下のように配慮しているミネラルサプリもあります。
「栄養は多ければ良いとは限りません。だから日本人に十分足りている成分や過剰摂取の心配がある成分は、あえて配合していません」
パッケージの裏や商品のWEBページに記載してあることが多いので、よく見て判断しましょう。
毎日続けやすいものか
ミネラルは体内で合成できないため、毎日バランスよく摂取する必要があります。そのため、サプリメントで摂る場合には続けやすいものを選ぶことが大切。「無理のないコストか」「飲みやすい量・形状か」などをチェックし、長く続けられるものを選びましょう。
体内に吸収されやすい設計になっているか
配合量だけではなく、吸収率まで配慮されたものを選びましょう。ミネラルの中には、吸収されにくい成分もあります。一緒に摂ることで吸収率が高まるミネラルや、吸収を助ける他の栄養素が含まれているサプリメントがおすすめです。
栄養素等表示基準値に対応しているか
配合されているミネラルの量が、栄養成分の摂取量基準である「栄養素等表示基準値」に対応しているか確認を。不足しがちな成分がきちんと含まれているか、過剰摂取の心配がある成分が必要以上に含まれていないかもチェックできると安心でしょう。
安全基準が守られているか
直接、口に入れるサプリメント。安全な製品でなければ、安心して続けることはできません。自社内で製造に関わる安全基準や体制が設けられているかどうか、しっかりチェックをしましょう。安全な原材料が使われているかなども確認できるとより安心です。
相談できる窓口があるか
サプリメントを摂っていると、飲み合わせの注意点や成分に関する疑問が出てくるもの。サプリメントの製造・販売元に、疑問やお悩みを気軽に相談できる窓口があるかどうかを確認しましょう。サポート体制が充実していると、安心して続けられます。
5. ミネラルをサプリで摂る場合の注意点
ミネラルの吸収を邪魔することなく、より効率的に摂取するための注意点をご紹介。サプリメントを摂り始める際に、まずは知っておきたいポイントです。
1日の摂取量を守る
サプリメントは、設定されている1日の摂取目安量を守って摂りましょう。ミネラルは、摂取量が多すぎても体の不調や副作用を招く場合があります。摂取目安量を、毎日継続して摂ることが大切です。
水かぬるま湯で摂る
ミネラルの吸収に影響を与えないためにも、サプリメントはなるべく水やぬるま湯で摂りましょう。お茶やコーヒー、牛乳など、水以外で摂取するとミネラルの吸収が阻害する場合があるので注意をしてください。
飲み合わせに注意する
普段から服用している薬や摂取している健康食品がある場合には、飲み合わせにご注意を。サプリメントは医薬品などと併用することで栄養素の吸収が悪くなったり、薬の副作用が強く現れたりする場合があります。医師や薬剤師、専門の窓口などに相談できると安心です。
6. まとめ
元気な毎日に欠かせないミネラル。さまざまな種類のミネラルをバランスよく摂ることで、効率よく体内に吸収されることが期待できます。この記事を参考にミネラルが豊富な食材やライフスタイルにあったサプリメントを選んで、日々の健康にお役立てください。