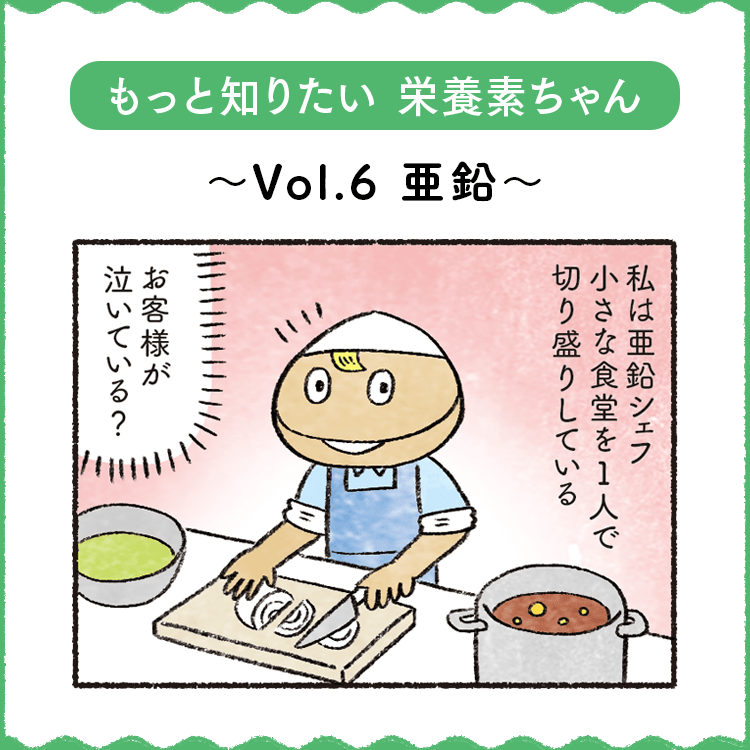亜鉛にはどんな効果があるの? 多く含まれる食品例や、摂る際の注意点を解説
健康の維持に欠かせないミネラルである亜鉛。必要な栄養素であることはわかっていても、どんな効果があって、どんな食品からどの位の量を摂るべきかなど、知らないことも多いものです。
そこで、この記事では亜鉛の働きや豊富に含まれている食材、摂るときの注意点などをご紹介します。また、サプリメントで亜鉛を摂る場合のポイントについても解説していきます。
1. 亜鉛とは
亜鉛は必須ミネラルの一つで、体の成長と維持に欠かせない栄養素です。細胞の新陳代謝に関わる200種類以上の酵素を構成し、細胞の新陳代謝やたんぱく質の合成をサポートしています。
骨や皮膚、粘膜、味蕾(みらい)といった、細胞の新陳代謝が活発におこなわれている器官では特に亜鉛の働きが重要となります。そのため、亜鉛が不足して細胞の代謝がスムーズにおこなわれなくなると、子どもの成長や皮膚の健康や味覚に影響を及ぼす可能性があります。
成人の体内にある亜鉛の量は約2gと微量ですが、体内で合成できないため食品やサプリメントなどで摂取する必要があります。吸収率が約30%とそれほど高くないこともあり、日本人に不足しやすい栄養素の一つともいわれています。
2. 亜鉛を摂ることで期待できる効果
細胞の新陳代謝をサポートする亜鉛。しっかりと摂れていると、体内でさまざまな働きをもたらしてくれます。ここでは、皮膚・粘膜の健康と味覚を正常に保つはたらきについて解説します。
皮膚・粘膜の健康維持
皮膚や粘膜のもととなる栄養素はたんぱく質ですが、亜鉛にはそのたんぱく質の代謝や合成を促す働きがあります。亜鉛を不足なく摂ることで皮膚の新陳代謝を正常にし健やかな肌へと導きます。
また、亜鉛は傷の修復に必要なコラーゲンの合成にも関わっているため、傷ついた皮膚や粘膜の修復がスムーズになります。傷の治りを早くしたり、口腔内の傷にも期待ができす。
皮膚も粘膜も新陳代謝が活発なため、積極的に亜鉛を摂ることが健康な皮膚・粘膜の維持につながるといえるでしょう。
味覚を正常に保つ
亜鉛は味を感じるための「味蕾(みらい)」という器官の新陳代謝をサポートし、味覚を正常に保つ働きをしています。
味蕾の細胞は新陳代謝のペースが約10日ほどと、短期間で新しい細胞と入れ替わるため、常に亜鉛を必要としています。そのため、亜鉛を不足なく摂ることが味覚の維持にとても大切なのです。
極端なダイエットや偏った食生活は亜鉛不足の原因になり、味を正常に感じられない味覚異常となることも。ご飯をおいしく味わうためにも、亜鉛は重要な栄養素といえるでしょう。
3. 亜鉛は何から摂るといいの?
体内で合成できず、食品やサプリメントで摂る必要がある亜鉛。厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、亜鉛の1日の推奨量を以下のように定めています。
| 性別 | 1日の摂取推奨量 |
|
男性(18歳以上) |
10〜11mg |
|
女性(18歳以上) |
8mg |
|
妊婦 |
10mg(女性8mg+2mg) |
|
授乳婦 |
12mg(女性8mg+4mg) |
成人女性1日の亜鉛の摂取推奨量は8mg。この量の亜鉛を摂るためには、どんな食品を摂るとよいのでしょうか。
亜鉛を多く含む食品を積極的に食べる
できれば毎日の食事で摂りたい亜鉛。効率よく摂取したいと考えるなら、亜鉛が多く含まれる食品を選びたいものです。文部科学省の食品成分データベースを見ると、亜鉛が特に多く含まれる食品は以下のとおりです。
| 順位 | 食品 | 100g当たりの含有量(mg) |
| 1位 |
かきの缶詰 |
25.0 |
| 2位 |
かきの水煮 |
18.0 |
| 3位 |
小麦胚芽 |
16.0 |
| 4位 |
生かき |
14.0 |
| 5位 |
カキフライ |
12.0 |
| 5位 |
かつお塩辛 |
12.0 |
出典:文部科学省「食品成分データベース」 ※「成分」リストから成分名を選択
含有量が高く、亜鉛の補給にぴったりなのが「かき」です。缶詰や水煮、生食などで日々の食事やおつまみなどに取り入れやすいのがうれしいポイント。かきが苦手という方は、牛ひき肉や牛肩ロースなども含有量が高くておすすめです。
成人女性1日の亜鉛の目安量8mgを摂るにはかきの缶詰で約33g(1/2缶程度)、牛ひき肉で約100g(標準的なハンバーグ1人前程度)、牛肩ロースで約120g(しゃぶしゃぶ1人前程度)を食べる必要があります。
亜鉛を多く含む食材については、以下のページでも解説しています。ぜひご覧ください。
亜鉛サプリメントで手軽に摂る
まずは普段の食事から摂るのが基本ですが、対象となる食品が苦手なものだったり、忙しくて1日に必要な量を摂るのが難しい日もあったりするでしょう。そんなときには、便利で手軽に亜鉛を補給できるサプリメントを取り入れるのも一つの手です。
サプリメントを選ぶ際には、続けやすいものを選ぶことが大切。「飲みやすい量・形状か」「無理なく続けられる費用か」などを確認して、長く続けられるものを選べるといいですね。
また、サプリメントを摂っているときに、気になることがあればすぐに相談できるメーカーを選ぶと安心です。サプリメントを摂っていると、飲み合わせの注意点や成分に関する疑問が出てくるものです。疑問やお悩みを気軽に相談できる窓口があると、安心して続けやすいでしょう。
4. 亜鉛を摂る際のポイント
ここからは過剰に摂取した場合の注意点や、一緒に摂ると吸収を妨げる食品など、普段の食事やサプリメントから亜鉛を摂取するときのポイントをご紹介します。
摂りすぎても、足りなくても、体に影響を及ぼす亜鉛ですが、安心して摂るために、注意点やポイントを知っておきましょう。
過剰摂取に注意する
通常の食生活であれば過剰摂取の心配はほとんどありませんが、薬やサプリメントなどで継続的に亜鉛を過剰摂取することで、急性中毒を起こすことがあります。発症した場合には、めまいや吐き気、胃障害、腎機能障害などがあらわれます。
サプリメントの摂取量=体内に吸収される量ではないものの、特に、妊娠中・授乳中の方は推奨量よりも多く摂取すると赤ちゃんへ影響が及ぶ可能性もあるため、1日の摂取目安量を超えて摂取しないよう注意しましょう。
また、持病などにより服用している薬がある方は、かかりつけ医に相談してから摂取できると安心です。特に、サプリメントで摂るときには飲み合わせが懸念される場合がありますので、事前に相談することをおすすめします。
亜鉛の吸収を妨げる食品もある
いくら亜鉛を多く含む食品を摂っていても、吸収を妨げる食品を一緒に摂取していると効率よく体に吸収できないことがあります。亜鉛の吸収を阻害する食品を知っておくと安心です。
<亜鉛の吸収を妨げる食品>
● 植物性食品(フィチン酸・食物繊維)
穀類や豆などの植物性食品に含まれるフィチン酸や食物繊維が腸管で亜鉛と結合し、亜鉛の吸収を阻害します。
● 加工食品(ポリリン酸)
ファストフードやインスタント食品などの加工食品に含まれるポリリン酸などの食品添加物が、亜鉛の吸収を阻害します。
● アルコール
アルコールは亜鉛の排泄量を増加させ、体外へ出て行ってしまう原因になります。
亜鉛の吸収を高める食品もある
亜鉛の吸収を阻害する食品や栄養素がある一方で、一緒に摂ると摂取効率がよくなるものも。亜鉛の吸収率をアップさせるためにも、合わせて摂るのがおすすめです。
<一緒に摂ると吸収率がアップする食品>
● 肉・魚(動物性たんぱく質)
亜鉛はたんぱく質と結合していると吸収率がアップするため、亜鉛を摂るときにはたんぱく質と一緒に摂るのがおすすめ。中でも、肉や魚などの動物性たんぱく質なら、亜鉛の吸収を阻害するフィチン酸や食物繊維の影響も軽減してくれます。
● お酢・梅干し(クエン酸)
クエン酸のキレート作用(ミネラルを体内へ吸収しやすい形に変える働き)により、亜鉛を吸収しやすくしてくれます。クエン酸を多く含むお酢や梅干しなどと合わせて摂ると効果的です。
● レモン(ビタミンC)
ビタミンCはクエン酸のキレート作用をサポートし、亜鉛の吸収率を高めてくれます。生牡蠣にレモンをかける食べ方は、まさに亜鉛の吸収率を高める食べ方といえます。
5. まとめ
皮膚や粘膜の健康を維持し、味覚を正常に保つために欠かせない亜鉛。日本人に不足しがちな栄養素でもあるため、意識して摂取を心がけたいものです。この記事を参考に亜鉛が豊富な食材や自分に合ったサプリメントを選んで、日々の健康にお役立てください。