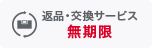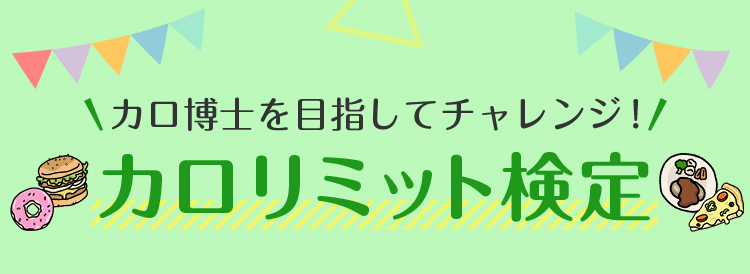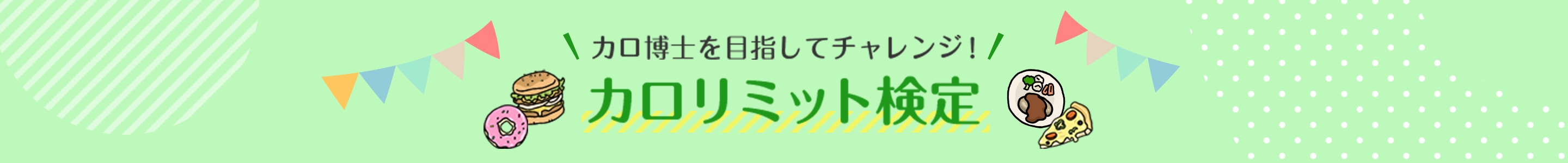問1 「カロリミット」が誕生したのはいつ?




問1の答え
B. 2000年
1996年10月に「カロリミット」の前身である「シェイプサポート」(写真左)が誕生。
「カロリミット」として新発売したのは2000年です(同中央)。
初代カロリミットはギムネマ&桑の葉、クローブ&キトサン配合でした。
Cの2014年は、「大人のカロリミット」(同右)が誕生した年です。
改良や進化を重ねて、誕生から20年以上愛されているロングセラー商品です。


問2
「カロリミット」「⼤⼈のカロリミット」には、
⾷事の「①」や「②」の吸収を抑えて、
⾷後の⾎糖値と⾎中中性脂肪値の上昇を抑える機能があります。
①と②に⼊る正しい組み合わせは?




問2の答え
B. ①糖 ②脂肪
「桑の葉イミノシュガー」「キトサン」「茶花サポニン」の3つを組み合わせることにより、⾷事の糖や脂肪の吸収を抑え、⾷後の⾎糖値と⾎中中性脂肪値の上昇を抑えます。
この3成分の組み合わせは特許を取得しています。
問3
「⼤⼈のカロリミット」に⼊っていて、
「カロリミット」に⼊っていない脂肪消費成分は?




問3の答え
C. ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、脂肪の代謝を助ける作用があります。
ちなみにA. キトサン、B. 茶花サポニンは「カロリミット」同様に「⼤⼈のカロリミット」にも含まれ、ともに⾷事の糖や脂肪の吸収を抑える作用があります。
問4
⽳埋め問題です。「⼤⼈のカロリミット」に配合されている
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、
(BMIが⾼めの⽅の)①を減らす機能があります。①に当てはまるのは?




問4の答え
B. 腹部の脂肪
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンを1⽇1回12週間毎⽇摂取したところ、腹部の脂肪が減少したという結果が報告されています※。
腹部の脂肪の代謝を助け、BMIが⾼めの⽅のBMI値の減少も期待できます。
※「⼤⼈のカロリミット」の機能性関与成分「ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン」による研究レビュー。


問5
⽢党じゃないから、
「カロリミット」「⼤⼈のカロリミット」は必要ない?




問5の答え
B. いいえ
⽢党でなくても、糖・脂肪には注意が必要です。糖は⽩⽶、パン、麺類などに多く含まれ、脂肪は肉・魚類、油脂、ドレッシング、ナッツ類など様々な⾷品に含まれています。
ドカ⾷い、早⾷いは糖・脂肪が吸収されやすくなるので、避けましょう。
問6
「カロリミット」「⼤⼈のカロリミット」のパッケージの
商品名下に書かれている共通のキャッチフレーズは?




問6の答え
B. ⾷⽣活をHAPPYに♪
⾷事をおいしく⾷べていただきたいという想いを込めて、「⾷⽣活をHAPPYに♪」のキャッチフレーズを採⽤しました。2020年10月のリニューアルより「⼤⼈のカロリミット」のパッケージにもこのキャッチフレーズがかかげられています。


問7 「カロリミット」「⼤⼈のカロリミット」の1回の摂取⽬安量は何粒?




問7の答え
A. 3粒
2020年のリニューアルにて、成分量はそのままに4粒から3粒に⽬安量を減らすことに成功しました。この時の「カロリミット」の試作回数は、なんと約100回! 体内効率設計と製剤の技術を駆使して試⾏錯誤を重ねた結果、ついに1回の⽬安量を減らすことに成功しました。


問8 「カロリミット」「⼤⼈のカロリミット」は併⽤してOK?




問8の答え
A. 併⽤してOK
「カロリミット」と「⼤⼈のカロリミット」、また同シリーズの「カロリミット茶」は、同じ⾷事での利⽤をしなければ、1⽇の中での併⽤はOKです。
併⽤する際は、⾷事の量や⾷事内容に併せて、組み合わせてみてください。例えば、夕食の量が一番多い方は、夕食に「大人のカロリミット」、朝食&昼食に「カロリミット」の組み合わせがおすすめ。「今日はランチにカルボナーラ食べちゃう!」など、ランチも食事量が増える日は、「カロリミット」を「大人のカロリミット」にかえるなど、いろいろお試しください。


問9
菓子パンや麺類など、短時間で食べられるものを選んでいるので、
「カロリミット」シリーズは必要ない。




問9の答え
B. いいえ
時短で簡単にといえば、コンビニなどで買う菓子パンや麺類などになりがち。パン・麺類には糖が多く含まれています。菓子パンは油脂をたくさん使用しているため、脂肪も多めに。麺類の中でもカップ麺のスープには脂肪が多く含まれていますので、より注意が必要です。


問10
おかずをたくさん⾷べていれば、
ごはんやパンなどの炭⽔化物(糖質)は⾷べなくてもOK?




問9の答え
C. バランス良く⾷べる
炭⽔化物(糖質)は、体や脳を動かすエネルギーになります。不⾜すると疲れやすく、摂りすぎると太りやすくなるといわれており、バランス良く⾷べることが⼤事です。
バランス良く栄養を摂るためには、主⾷、汁物、3つのおかず(主菜1つ、副菜2つ)の「⼀汁三菜」が良いとされ、昔から⽇本⼈の健康を⽀えてきました。主⾷を中⼼にいろいろな⾷品を組み合わせて作った汁物やおかずをまんべんなく⾷べることで、栄養バランスが整うように考えられています。また、旬の⾷材をとり⼊れることで、よりバランスの良い理想的な⾷事になります。


問11 三⼤栄養素とは、脂質、たんぱく質、もう1つは?




問11の答え
A. 炭水化物
炭水化物・脂質・たんぱく質の三大栄養素の主な働きは、体を動かすエネルギー源(カロリー)になることと、体を構成する組織を作ることです。
これに、体の調子を整える働きがあるビタミン・ミネラルを加えると五大栄養素となります。さらに、食物繊維は整腸作用など体の中で有用な働きをすることが注目され、第6の栄養素といわれています。
これらをバランス良く摂ることが大切です。


問12 油やバターなどに多く含まれている脂質1gは何キロカロリー?




問12の答え
C. 9kcal
脂質は三大栄養素の中で最もカロリーが高く、たんぱく質や炭水化物の約2倍のエネルギーがあります。
特にバターなどの乳製品やナッツなどの種実類、マヨネーズなどの調味料、洋菓子や菓子パン、スナック菓子、カレーやシチューなどのルーは、脂質が多い食品です。脂質の摂りすぎは、健康リスクを高める原因にもなりますので、注意しましょう。ちなみにたんぱく質、炭水化物の1g当たりのエネルギー量はともに4kcalです。
問13
年齢とともに減少する代謝量ですが、
「生命活動を支え、エネルギーを消費する」代謝の種類は何種類ありますか?




問13の答え
C. 基礎代謝、生活活動代謝、食事誘発性熱産生の3種
「基礎代謝」は、呼吸をするなど生命維持のための必要最小限のエネルギー代謝です。何もしなくても、寝ていても消費するので、効率的にエネルギーを消費するためには、基礎代謝を上げることが理想とされています。
「生活活動代謝」は、運動のほか、家事や仕事などの生活活動による代謝のことをいい、運動の有無や活動の強度、体格の差などにより代謝量は個人差が生じます。
3つめの「食事誘発性熱産生」とは、食事を消化・吸収する際に消費するエネルギー代謝です。食事を摂ると体内に吸収された栄養素が分解され、その一部が体熱となり消費されます。食後に体がぽかぽかするのはこの働きによるものです。このため食事をした後は、安静にしていても代謝量がアップします。
1日のエネルギー消費量の割合は、基礎代謝が約60%、生活活動代謝が約30%、食事誘発性熱産生が約10%で、基礎代謝が一番大きな割合を占めています。
問14
30~49歳の女性の1日の基礎代謝量(平均値)は、
15~17歳と比較すると、何kcal少ないでしょうか?




問14の答え
B. 160kcal
女性の1日の基礎代謝量の平均値は、30~49歳が1,150kcalなのに対し、15~17歳の女性は1,310kcalですので、1,310kcalー1,150kcal=160kcalとなります。ちなみに160kcalは6枚切りの食パン1枚に相当します。
体格にもよりますが、女性の基礎代謝量はおおむね12~14歳がピークで、以降は加齢とともに低下していきます。主な要因は筋肉などの除脂肪量の低下で、それに伴って代謝率も低下するため、以前と同じ⽣活や運動をしても消費するエネルギーは少なくなります。また、⽣活活動量の減少も要因の⼀つと考えられます。意識して体を動かすなど、代謝の維持を⼼がけましょう。


問15 代謝を上げる生活習慣は次のうちどれでしょうか?




問15の答え
C. 入浴
お風呂はシャワーだけですまさず、湯船にしっかりと浸かりましょう。⼊浴は体を温め、⾎⾏を良くする効果があり、代謝が上がるといわれています。40℃くらいのぬるめのお湯にゆっくり浸かり、1⽇の終わりにリラックスしながら代謝を整えるのがおすすめです。
代謝が低いと血流が悪くなることがあり、冷えや疲れなどにつながる恐れもあります。日々の生活の中で代謝アップを意識して、気軽に始められることからトライしてみましょう。